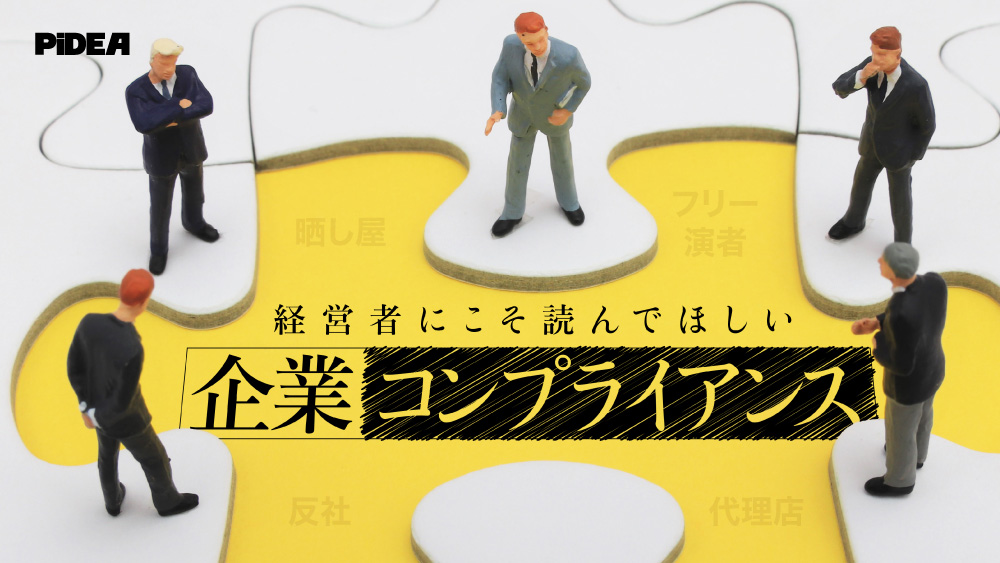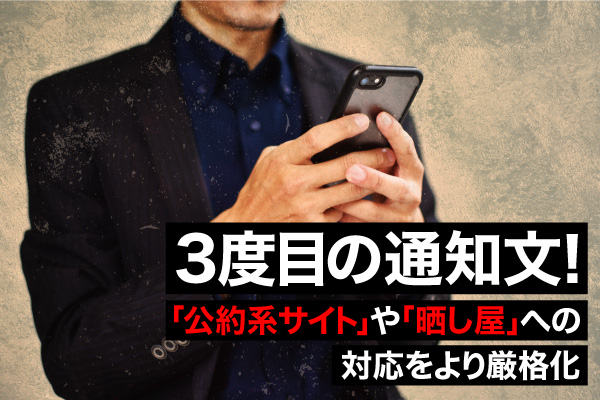「経営者にこそ読んでほしい企業コンプライアンス」ー全話まとめ
2022.11.16PiDEA連載
「経営者にこそ読んでほしい企業コンプライアンス」
パチンコ業界が社会から認められることには重要な意義があり、それを実現する上でもっとも重要なことがコンプライアンスの遵守だ。しかし、時として定められたルールを逸脱してしまったり、不適切な業者との望まない取引に巻き込まれてしまったりすることがある。混沌とする時代だからこそ、何が持続可能な業界を目指すためには必要なのか、改めて考えてみてほしい。本企画は、PiDEA本誌でそんなことを展開している。
大変光栄なことに、さまざまな企業や団体で本連載の記事を会議の議題として取り上げ語られることもあると聞く。本記事では、より多くの方々に利用していただくためにも、過去すべての連載を一箇所にまとめたアーカイブページを作成した。今後の連載も随時こちらに更新していきたいと思う。

知らないうちにキケンな取引が開始
「その業者さん大丈夫ですか?」
素性の知れない人気演者や晒し屋を使うことがホールの経営戦略上必要なのであれば、それはそれで良いが、そこには管理が必要である。「店長が呼び(使い)たがっているから……」というだけでハンコをついてしまう管理者はコンプライアンス上問題があると言わざるを得ない。
Vol.2
炎上するフリー演者と
パチンコホールがそれを回避する方法

「目立ってなんぼ」のフリー演者を
起用する想定外のリスク
個人を起用する場合、その人たちがやりとりの裏側を絶対に漏らさないという確証はない。むしろ、契約を切ろうとした瞬間に、彼らが店長から受け取ったメール、DM、LINEのスクリーンショットをネット上にバラまいてしまう事態もありえない話ではないのだ。
Vol.3
まとめサイトで取り上げられ炎上も、
それでも〝晒されたい〟ですか?
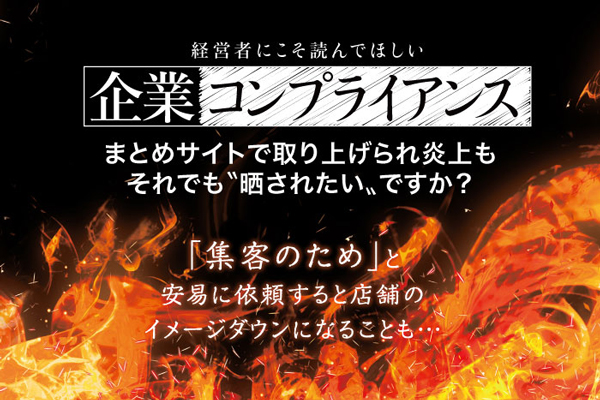
晒すのは是か非か!?
SNSにはびこる晒し屋の実態
晒し屋という呼称自体のイメージが悪く、不正行為のように捉えられがちだが、明確なルール、線引きがない。法や規制がSNSの進化のスピードに追いついていないため、現状では行為自体はグレーのような扱いとなっている。ただしそれは晒し屋とホールの間に金銭の授受がない場合に限る。ホールが依頼して晒し屋がツイートするのは広告宣伝にあたる。ホールが晒し屋に対してお金を支払っている証拠が見つかった場合、内容によってはホールが法的責任を負うことになるだろう。
Vol.4
フォロワーが数千人いれば
演者として成立「それでいいのか?」
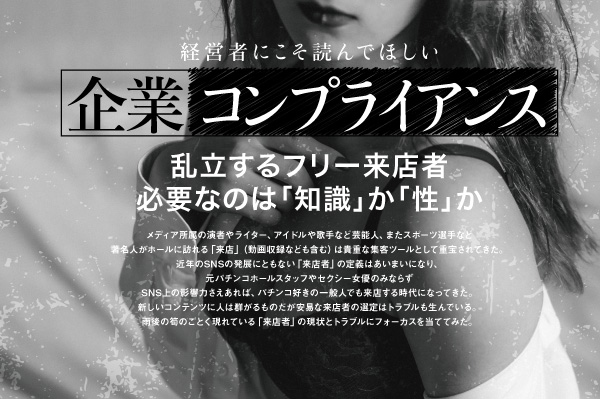
フォロワーが数千人いれば
演者として成立「それでいいのか?」
状況はもはやなんでもありといったところまで差し掛かっている。Twitter上で胸の谷間を出し、「パチンコ好き」といったような言葉を紹介文に並べ立て、その色気に寄せられた男子諸君がフォロワーとなり、そのフォロワー数を担保として演者業を始める。これが、今や「量産型エロ系女演者」などとネットで揶揄されている要因の1つだ。本来パチンコ・パチスロの専門家が取材に行くから成立する「来店」を、乳見せで誤魔化すという行為に加担することは、パチンコ業界が自らの手で価値を貶めているといっても過言ではない。
Vol.5
コンプラ重視なのは仕方ない、
それでも必要不可欠なのが広告宣伝
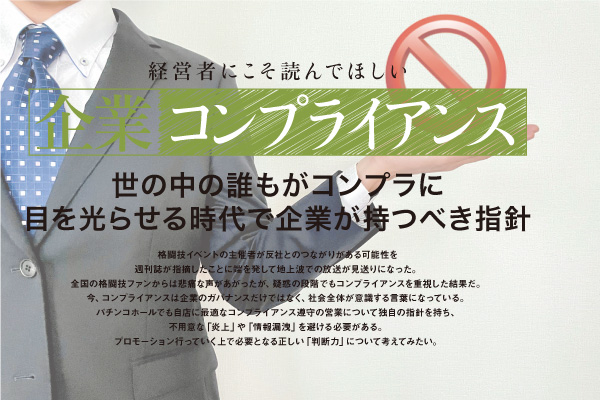
コンプラ重視なのは仕方ない、
それでも必要不可欠なのが広告宣伝
TV局の「コンプラ重視」は一方で、視聴者離れという弊害も引き起こしてしまっている。広告宣伝という企業にとって必要不可欠な活動をするにあたって、明確な物差しや基準を持つことが重要なのではないだろうか。これはパチンコ業界に限らず、すべての業種にとっても同じことが言える。
Vol.6
複雑化する商取引で
望まない企業と関係ができる危険性
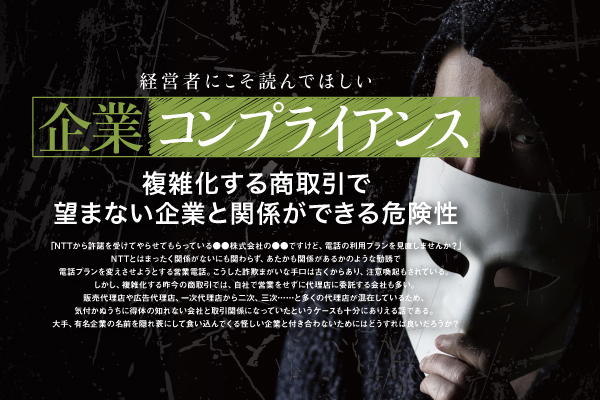
複雑化する商取引で望まない企業と
関係ができる危険性
身に覚えがない会社との取引が発生してしまうリスクがある中で、企業が一番気をつけなくてはならないのが、反社会勢力との付き合い(取引)である。国内では、1991年に反社会勢力取締強化のために「暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律」(暴対法)が成立し、その後、反社会勢力の手口が巧妙化したことを受けて、2007年には「犯罪収益移転防止法」が成立。反社会勢力が不当に儲けようとする行為は取り締まりが強化され厳しくなっているものの、法の目を掻い潜るように手口が巧妙化しており、初見では反社かどうか、気付かないこともありえるだろう。
Vol.7
無知なフリー演者や晒し屋の起用は
「インボイス」制度の導入で
危険度アップ
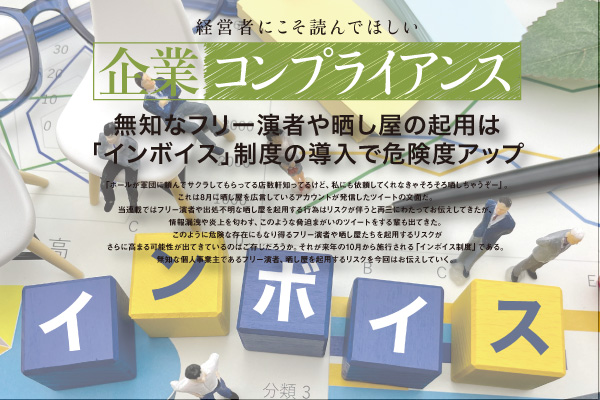
無知な演者や晒し屋の「税金」を
ホールが支払うことになる!?
パチンコホールは遊技機メーカー、周辺機器メーカー、販売会社、中古機会社、景品会社、メディアなど多数の業者と取引をしている。大多数の取引業者は「適格請求書発行事業者」の申請をするだろう。
しかし、もしかすると取引業者の中で課税売上が1000万円に満たないところが今まで通り益税の権利を主張し、「適格請求書発行事業者」の申請はしたくない、つまり「僕らの税金はホールさんが払ってくださいね」となるかもしれない。ホール側からすると、この状況を受け入れるべきだろうか。
答えはNOだ。
Vol.8
多様化する働き方を救う
「フリーランス保護新法」は
何をもたらす
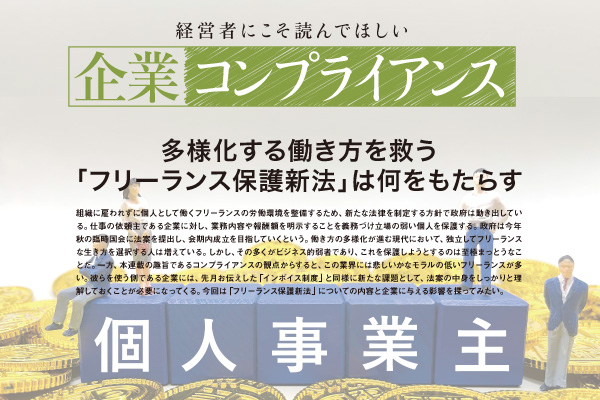
多様化する働き方を救う
「フリーランス保護新法」は何をもたらす
今回のフリーランス保護新法に関していうと、間違いなくフリーランスの立場からすれば歓迎すべきものであるが、逆に企業側からすると、「インボイス」同様にやらなければならないことが増える法案といえるだろう。口約束で成立させていた仕事や急遽対応に迫られた時だけ利用する仕事など、気軽に発注していた仕事に制約が付与されることになるのだ。報酬や契約期間を書面や電子データで明示・交付が必須となれば、新たな業務が増加してそれも負担となるだろう。
Vol.9
機密情報漏洩のリスクヘッジ
「不正競争防止法」が今注目されるワケ
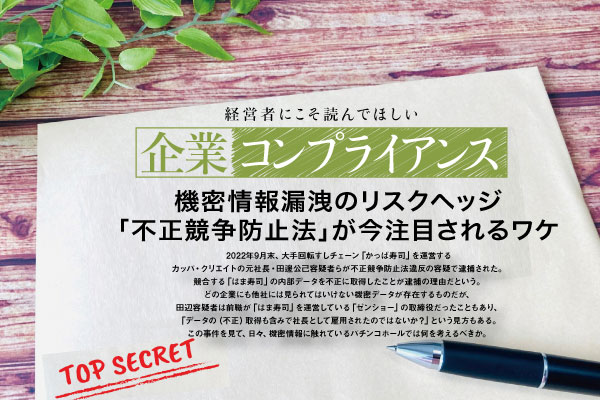
移籍や独立時に前職の
機密情報を漏らす行為
「それ犯罪です。」
過去に勤めていた会社の機密情報を持ち出して、再就職した企業でそれを活用するのは「営業秘密の侵害」や「限定提供データの不正取得等」という不正競争防止法における明確な罪となる。企業はこうした問題を防ぐために、入社時に「●年間は同業他社へ転職しない」などの誓約書を作成し、社員とその書類を取り交わして契約することが一般的だ。
Vol.10
ついに行政がが名指しで言及した「晒し屋」
改めて起用のリスクが問われる

量定D(20日の営業停止)よりも
重い処分が下される可能性
2022年10月19日、都遊協が開催した遊技場経営者研修会の中で警視庁保安課風俗営業係の担当官による「広告宣伝」に対しての話があった。その中で担当官は、「サイト運営会社や晒し屋ではなく、店舗側に行政処分が下される可能性がある」と発言。公の場で行政が「晒し屋」という単語が使ったこと自体が初めてのことであり、ホールは改めて彼らを起用することに対するリスクを考慮し、警戒レベルを高めていかなくてはならなくなったのである。
Vol.11
今日もどこかで誰かが炎上中
それでも止まらないのはなぜなのか?
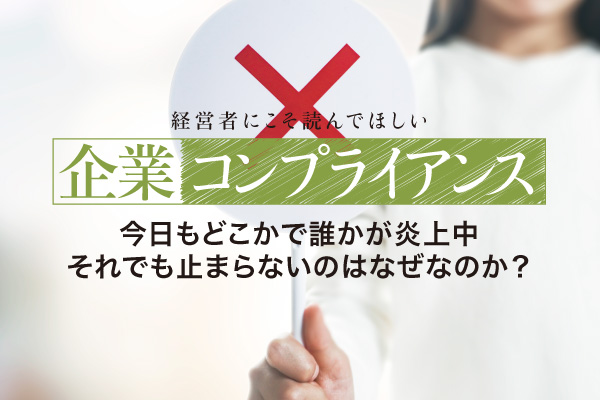
誰もがTwitterやYouTubeなどのSNSを活用する時代で、企業もそれらをプロモーションで使うことはなんら珍しいことではなくなっている。
誰でも簡単に使えるからこそ、企業が使う場合はコンプライアンスを徹底した上でリスクを考えて活用すべきであると再三お伝えしてきたが、2022年も業界内外で炎上する案件が多数見受けられた。今回は新年号ということもあり、初心に立ち返ってSNSにまつわる炎上ネタを反面教師としてピックアップした。改めて新年こそは安全で効果的なSNSの活用方法を模索していただきたい。
Vol.12
業界で重宝されるSNSに危機到来!?
Twitterを取り巻く環境の変化
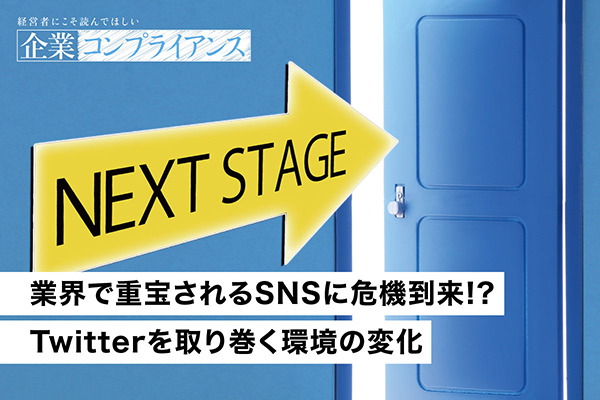
激変した「Twitter」の環境
それでもやっぱり使い続けますか?
国内では4500万人のアクティブユーザーを抱えるTwitter。昨年イーロン・マスクによって買収され話題になったと思ったらいつの間にかインプレッションが公開になっていた。
Vol.13
バズりと炎上の境界線
見極めたいSNS運用の効果
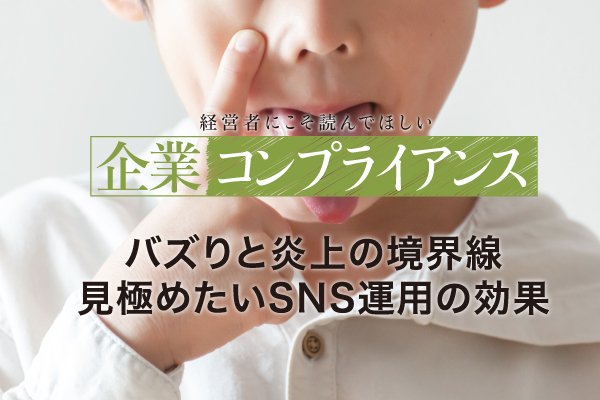
軽い気持ちのイタズラが大炎上
なぜおバカ行為が続くのか
TwitterやTikTokに動画が投稿されて回転寿司でのイタズラ行為が立て続けに露見して話題になった。SNS普及し始めた10年前から炎上しているにも関わらず迷惑行為が後を絶たない理由はなんなのか。
Vol.14
着々と外堀が埋まりつつある
個人事業主の脱税対策
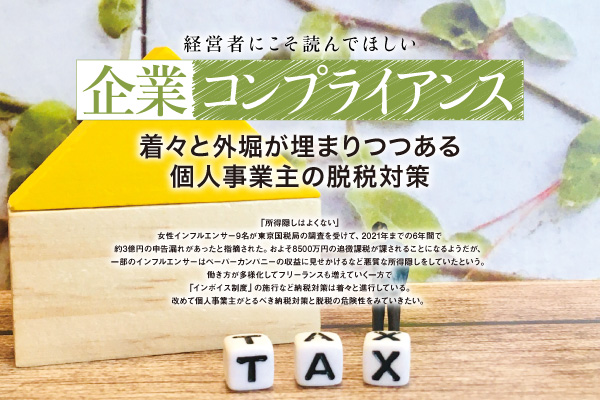
華やかなインフルエンサーも
税金を逃れるために四苦八苦?
化粧品や健康器具などをSNSで紹介することで対価を得ているインフルエンサーに国税局のメスが入った。華やかに見えて憧れの職業と言われているが脱税の手法は見苦しいものだった。
Vol.15
近しいところに危険アリ!?
〝巻き込まれ炎上〟が増加中
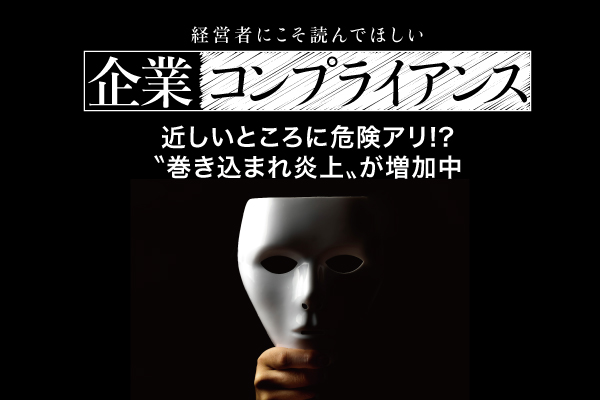
健全化を掲げてもすり寄ってくる
業界にはびこる怪しい面々
全国で「暴排条例」が施行されてから10年以上が経過。パチンコ業界も健全化を掲げて、クリーンな業界を目指してきているが、それを阻む怪しい輩は後を絶たず、むしろ加速している。
Vol.16
広告なの広告じゃない⁉︎
ステマ規制が間近に迫る
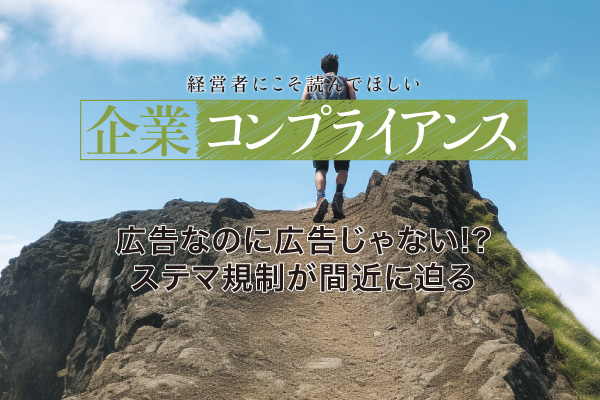
誤解を与える広告宣伝はNG
景表法の中身を見直そう
消費者に誤解を与える広告表示は常に規制の対象となり景表法は都度改正されてきた。
今回の「ステマ規制」もその1つだが、どんな事例が問題となり、どんな罰則があるのだろうか?
Vol.17
リミットまで約3ヶ月
インボイスやステマ規制の影響
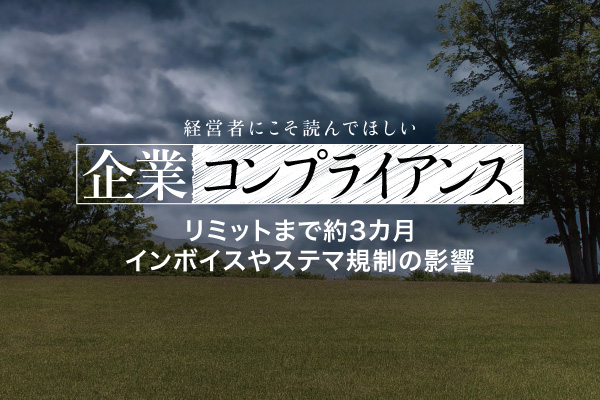
著名声優が廃止を涙で訴え
個人には死活問題のインボイス
「進むも地獄退くも地獄」。フリーランスで仕事をしている人たちは「インボイス制度」をそう例える。
多くの個人事業主が声高に廃止を訴えるが、同制度の開始時期は刻一刻と迫る……。
Vol.18
大手中古車販売会社の不正で

現場に〝責任なすりつけ辞任〟
コンプラ軽視と売上重視の顛末
大手中古車販売会社「BIGMOTOR」による意図的な車両損壊で保険金を不正需給した問題が世間を賑わせている。
元社長は「経営陣は知らなかった」とうそぶいたが、知らないで済む問題ではない。
この他、気になるテーマや事件の情報、記事の感想などについては、気軽に当サイトの問い合わせフォームか、もしくはTwitterのDMからご連絡を。
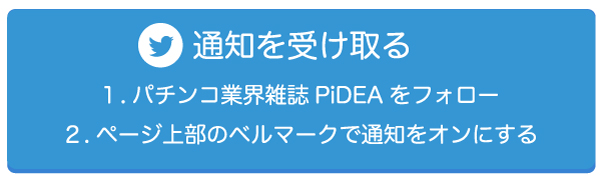
 LINE
LINE