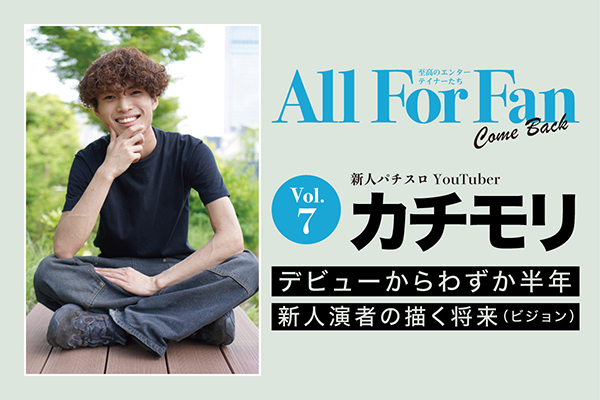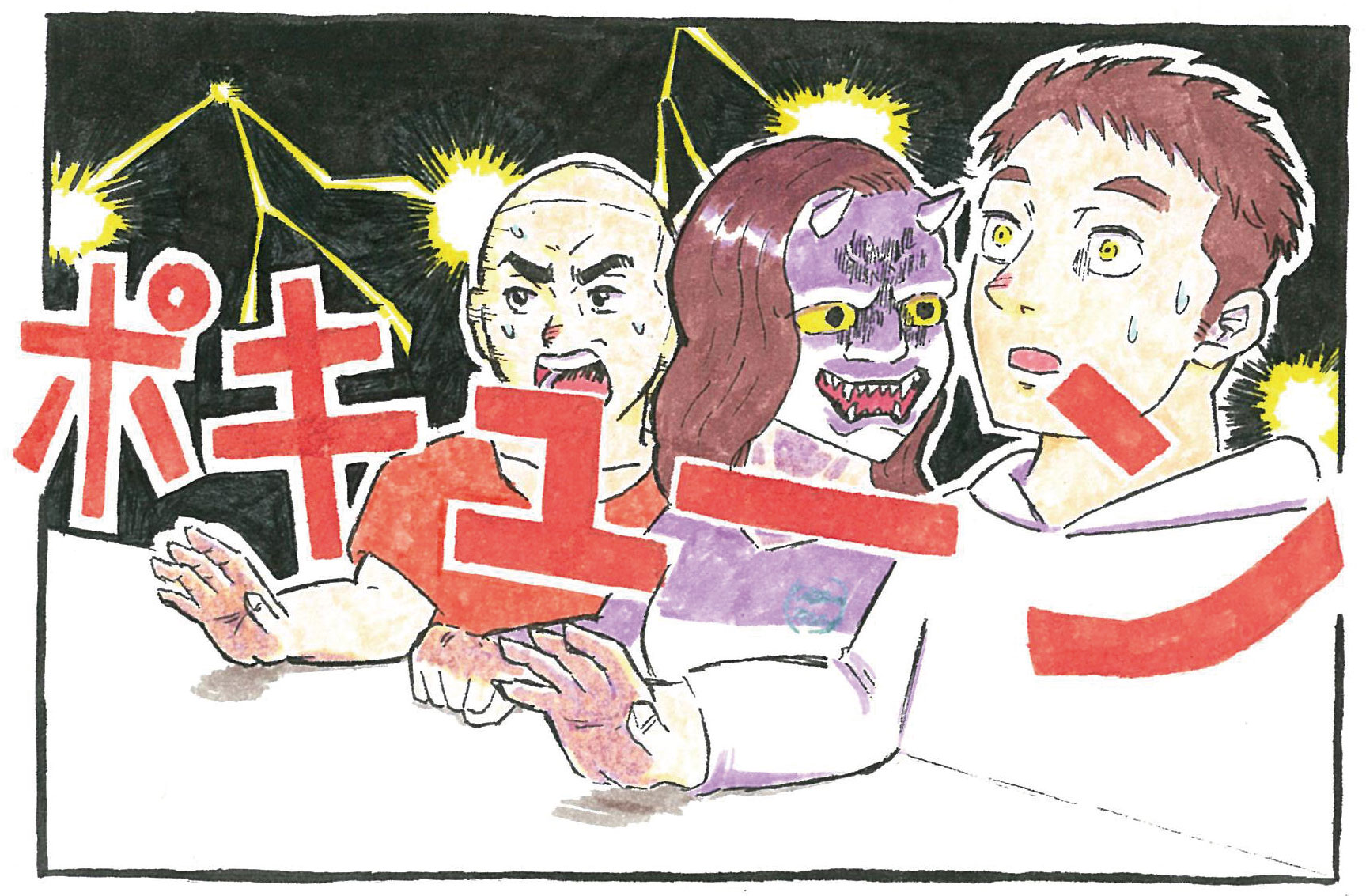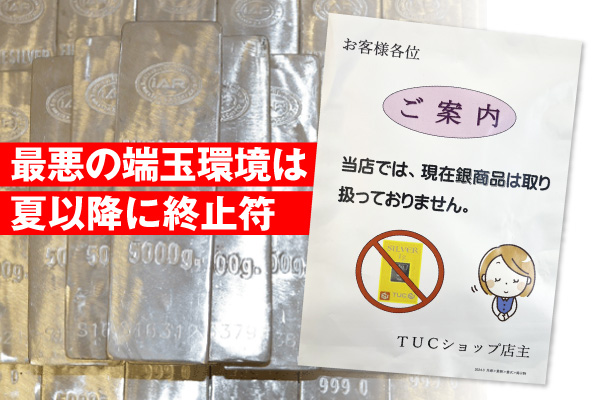昭和の大学生の遊びと言えば、パチンコか麻雀が王道だったが、今の大学生はその両方をやらない。
あるアンケート調査で自分の子供に覚えて欲しいレジャー・覚えて欲しくないレジャーについて聞いている。
予想していたことだが、パチンコ、麻雀、競馬などのギャンブルを勧める親はさすがにいない。逆に子供にやって欲しいのは、登山、ハイキング、スキー、ゴルフ、野球・サッカー観戦など健全で健康的なものが多い。
ま、当たり前の結果だ。今の若者がギャンブルをやらないのは、そういう親御さんの下で育った環境もあるのかも知れないが、ギャンブルイメージが良くない。
ねとらぼ調査隊の「2020年若者の〇〇離れ」の調査で、堂々の第1位はギャンブルだった。63.3%が興味がない、と回答している。ギャンブル依存症などのリスクの認知も広がり、距離を置いている若者が多くなった表れでもあろう。
ちなみに2位はタバコで60.7%が興味ない、3位はクルマで39.2%が興味ない、と続く。
パチンコも麻雀もギャンブルのカテゴリーに入るが、ホールや雀荘とタバコは切り離せない関係性があった。
興味がないツートップの条件が揃うパチンコや麻雀に興味を持ってもらえるはずもない。
で、共に客の高齢化が進むパチンコ業界と麻雀業界だが、麻雀業界が2018年から麻雀を知的スポーツとして麻雀人口を増やすことを目的に開催したのが麻雀のプロリーグである「Mリーグ」だ。これはAbema TVで中継され「観る麻雀」の普及に一役買っている。500万人が視聴した経験があり、うち、300万人は麻雀未経験者だった。
自動雀卓メーカーは2018年から「ニューロン子供麻雀教室」を開校し、小・中・高生を対象に麻雀のカルチャー講座を開いている。麻雀はパズル・確率・心理戦といった様々な要素を盛り込んだ最高峰の頭脳ゲームでもある。将棋や囲碁のような知的趣味として健全に楽しむ麻雀は、情操教育の機会としても優れている、と言われている。
パチンコ業界ほどの資金力がない麻雀業界でも、こうして、若者に麻雀に興味を持ってもらうための努力を行っている。
麻雀が頭脳スポーツという新たなイメージを発信するなら、パチンコもこれに匹敵する新たなイメージづくりが必要だ。
「JRAはテレビCM戦略で若者が参加しやすいイメージに変えた。パチンコ業界はみんなから愛されるキャラクターづくりが必要」と話すのはシンクタンク関係者。
で、本人の口から出たのは突拍子もない人物の名だった。
「不倫疑惑で清純なイメージが崩れた福原愛ちゃんをパチンコ業界が使うのも一つの手。泣き虫愛ちゃんのイメージで日本中に愛されていたが、今回の騒動で非常に使いにくくなっている。こういう時こそパチンコ業界が手を差し伸べて助ける。彼女なら長期コンテンツとしても使える。メーカーは卓球愛ちゃんのパチンコ台を作るもよし」
現実性は極めて薄いが、何らかの形でイメージを変えることに業界首脳は本腰で取り組まなければならない。
 LINE
LINE