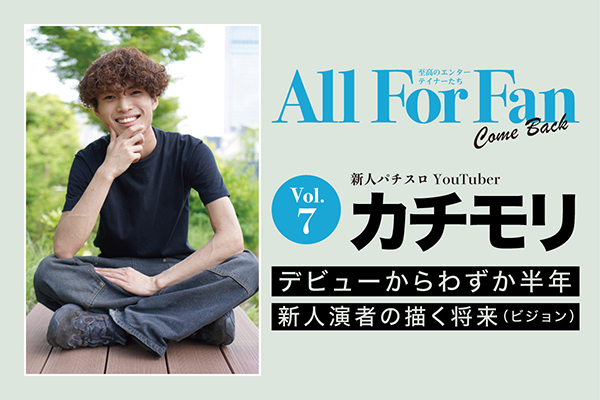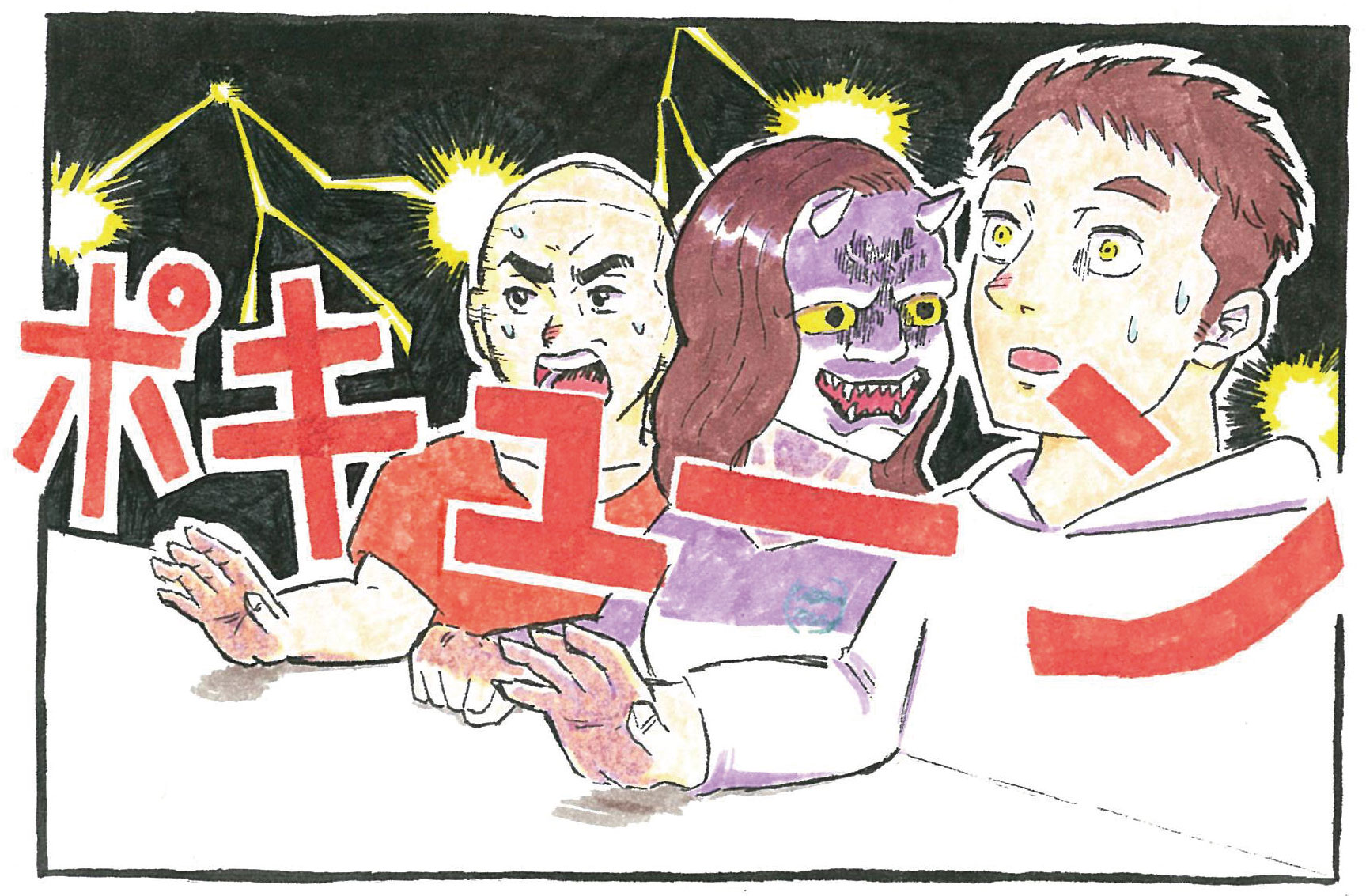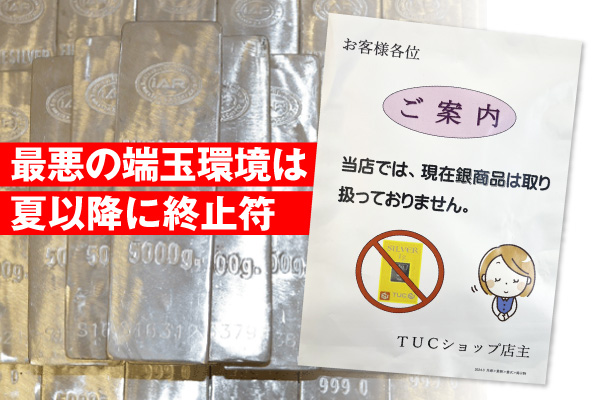世界のクルマの潮流は電気自動車(EV)へと向かっているが、日本のメーカーはハイブリッドに拘り過ぎて出遅れた感がある。トヨタがハイブリッドの特許をすぐに公開していたらEVの流れも今ほどではなかったかも知れないが、エネルギー政策は国際政治が絡むのでそれに負けてしまったきらいもある。
菅首相が2020年10月の所信表明演説で掲げた2050年までのカーボンニュートラル宣言を実現するには、EVだけでなく、水素エネルギーの活用が不可欠となってくる。
水素を新エネルギーの“国策”に位置付ける点からも燃料電池車(FCV)が注目されている。
FCVは水素を空気中の酸素と化学反応させて電気を発生させモーターを駆動させる方式だ。排出物は水だけ。
日本ではトヨタの「MIRAI」やホンダの「クラリティ」が市販されている。2代目となるMIRAIは水素搭載容量が4.6kgから5.6kgに増えたことなどもあって1回の充填で850キロも走ることができる。
その一方でネックは、FCVはMIRAIで車両価格が800万円前後、と高いこと。
そこで、高価な燃料電池ではなく、水素をエンジンの中で燃焼させる発想が水素エンジンだ。2009年にはマツダが水素ロータリーエンジン搭載の「プレマシー」や「RX-8」を市販に漕ぎつけた。時期尚早だったが、ここにきて水素ロータリーエンジンが再び注目されている。
水素エンジンをさらに加速させるのがトヨタだ。
5月21日から23日の3日間に亘って富士スピードウェイで開かれた「NAPAC 富士SUPER TEC 24時間レース」に、トヨタは水素エンジンを搭載した「カローラH2コンセプト」で参戦した。
水素エンジン車で24時間レースに挑んだ世界初の試みは、目標としていた完走を果たし、成功裏に終わった。
トヨタの水素エンジンは、ガソリンエンジンから燃料供給系と噴射系を変更し、水素を燃焼させることで動力を発生させるものだ。同社のMIRAIに使用されている燃料電池とは、まったく異なる。長年蓄積してきた技術やノウハウを生かせるのは大きなメリットだ。また、水素貯蔵タンクや水素補充の仕組みにはFCVの技術が使われる。
水素エンジン車はFCVよりも安価に設定できる可能性が高い。しかも、エンジンで使用する水素はFCVほど高純度なものでなくてもいい。ハイオクがFCVならレギュラーが水素エンジン車ということになる。つまり、水素エンジン車はFCVと比べるとイニシャルコストもランニングコストも抑えられた、庶民のクルマになる可能性がある。
EVは万能ではない。今年の冬、大雪で新潟の関越道で1000台以上が52時間も立ち往生した。幸いEV車はいなかったが、電池容量の少ないクルマだと20時間、大容量のリーフで60時間が限界だ。ガソリンなら立ち往生中でも自衛隊が給油することもできるが、充電はできない。
つまりEVのネックは充電だ。一般的には家庭で夜間に充電するわけだが、遠出した場合、充電するのに急速でも30分はかかる。
一方の水素は満タンまでに5~10分というのがEVに対するアドバンテージだ。
カーボンニュートラルを目指す政策と水素エンジン車の普及によって、今後は水素ステーションが増えることが予想される。
パチンコ業界が模索する新規事業の一つに水素ステーションはあり?
 LINE
LINE