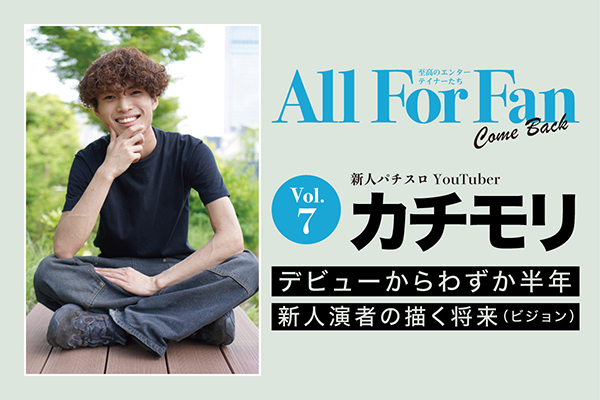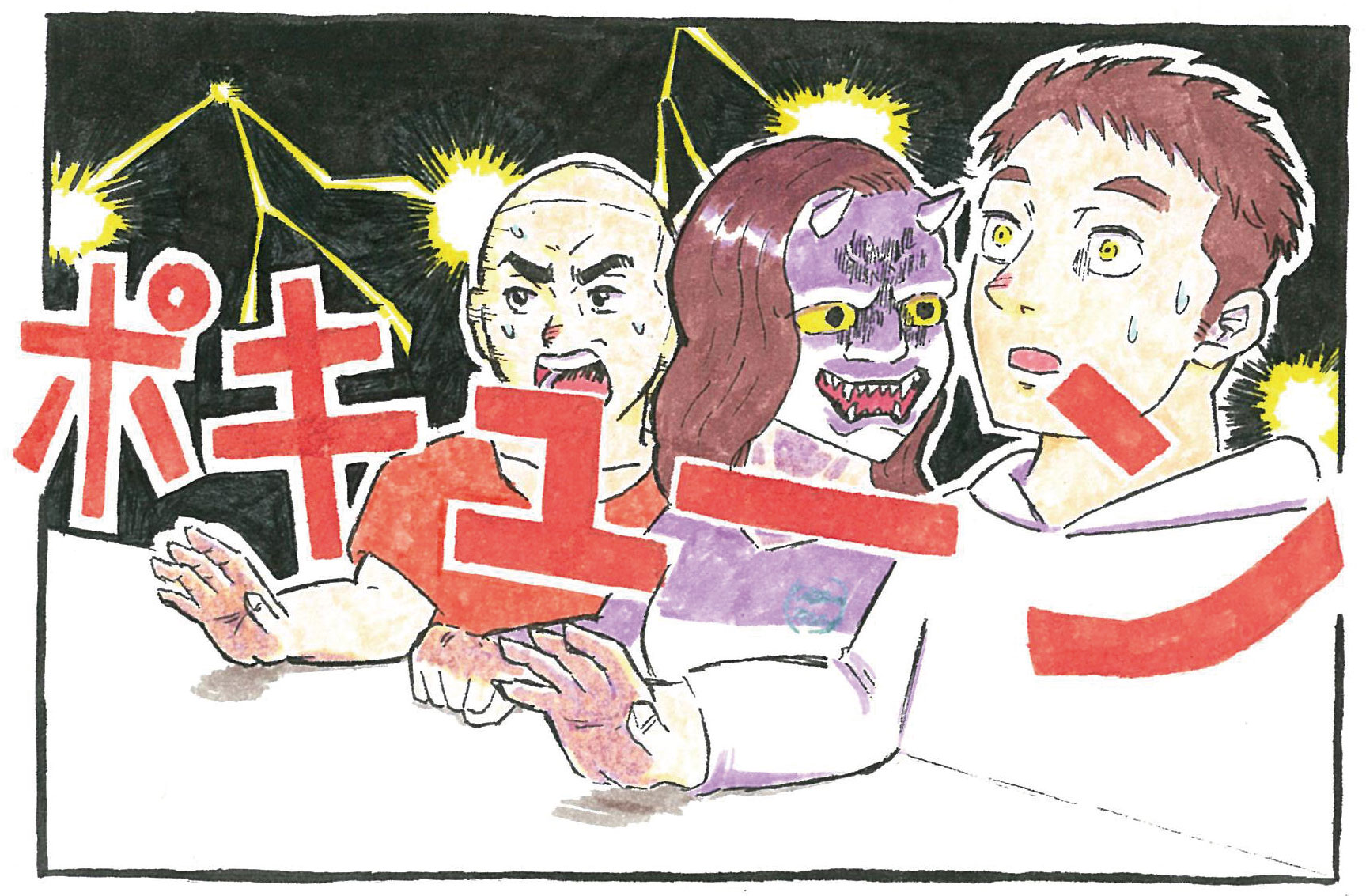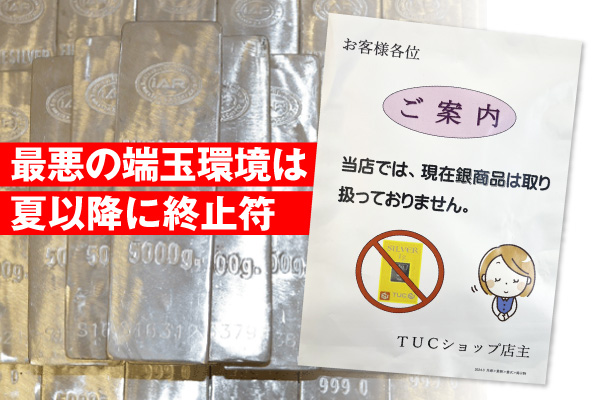前回は≪6.ライトユーザー視点の活動強化≫について書きました。
ビギナーの方が新規でファンになる道筋としての活動強化はもちろんのこと、ライトユーザーの方々が離反せず、楽しみの一つとして関わり続けて頂く活動がとても大切です。
「つまらなくなった」という気持ちは、毎日来店するお客様にも起こりますが、ライトユーザーのお客様は「好きな機種が無くなった」「好きな機種が見つからない」「自分に合った機種が探せない」など、そもそも機種に詳しくないお客様は離反の可能性が高い状態です。
この課題に対して、『新』営業スタイルの1~4をお店で実践していくことが大切です。
そして、今回は≪7.効率と非効率の融合≫です。
業界全体、全国の各地域の市場でファンの離反が長らく続いています。
ファンが多かった時代は、利益にゆとりがあったので一見無駄だと思われることに対してもお金を投資して、さまざまな挑戦ができました。
遊技機に関しても、ハネモノ・権利モノ・セブン機・一発台・アレパチ・・・・など、さまざまな嗜好に合わせて、各種のファンの多少に応じて機種を設置していました。
しかし、費用対効果という考え方から、「同じ機械台を使うなら、より稼げるものに投資をする」という方向に流れていきます。
これは自然なことですが、≪稼げる≫という点において、瞬間的に稼げる額が大きいのか、長期的に稼げる額が大きいのかを常に考える必要があります。
機種という商品には、性能やタイプによって商売上の目的のウェイトが異なります。
集客目的・稼働目的・粗利目的・売上目的・・・・などなど、長期と短期の両面で考えるものになります。
ファンを離反させないことと、新規ファンを増やす取組みのバランスを『お客様視点』で割合として考えていけば良かったのですが、とにかくファンの割合が多い機種性能などへの投資に偏り(効率)、ファンの割合が少ない非効率なものを排除していった流れがあります。
メーカーさんも、売れるものを作りたいという基本的なことがあるので、非効率な機種は蔑ろにされていきます。
機種のことに関して書きましたが、これはお店の経費削減によって失われた非効率のものも沢山あります。
そもそも、効率は同じ労力で以前よりも効果を高めることが目的ですが、労力をかけても効果が高くないものに関しては、【目先の効果か、長期的な効果か】をよくよく考える必要があります。
多くの非効率で労力がかかるが、長期的にはとても重要な取組みが失われてきました。
簡単な例えとしては、経費削減のためにスタッフの人数を減らした結果、一人当たりの粗利額は上がっても、お店の魅力づくりとしてのお客様との接触回数は下がっていきました。
効率を一人当たりの粗利額を目的にした場合は、短期的には良いのですが長期的にはお客様をサポートできなくなり離反を起こすことになります。
あくまでも例えなので、人を増やせばいいということではなく、人数を減らしてもお客様との接触回数を減らさない効率も考える必要があるというものです。
このようなこと以外にも、重要なコトは“パチンコという商売において非効率だが重要なことは何か?”を考え、これまでに捨ててしまった重要な取組みを、効率よくやれる方法は無いか?を検討して実施していくことです。
とても抽象的で分かりにくいコラムになりましたが、商売として失ってはいけない取組みを再度振り返り、効率と非効率の融合でお店の魅力を高めていきましょう。
【7つの『新』営業スタイル】は下記の内容です。
1.コト視点のコーナー作り
⇒自分の好みに合いそうなタイプをせる
2.台が分かるを実現する
⇒タイプが分かった後に、どうなれば勝てるのかイメージできる
3.接客スタッフ⇒営業スタッフ
⇒スタッフが自分の好みを探すサポートをしてくれる
4.ストック系機種作り
⇒新台以外にも、自分の好みの機種レパートリーが増える
5.ビギナー視点の活動強化
⇒ビギナーの友人を連れてきたときに、おすすめできるコーナーがある(ビギナーの人が楽しめる体験価値がある)
6.ライトユーザー視点の活動強化
⇒たまにしか遊ばない人でも自分に合いそうな機種がいつでも探せる
7.効率と非効率の融合
⇒多種多様なニーズや顧客層をサポートする
 LINE
LINE