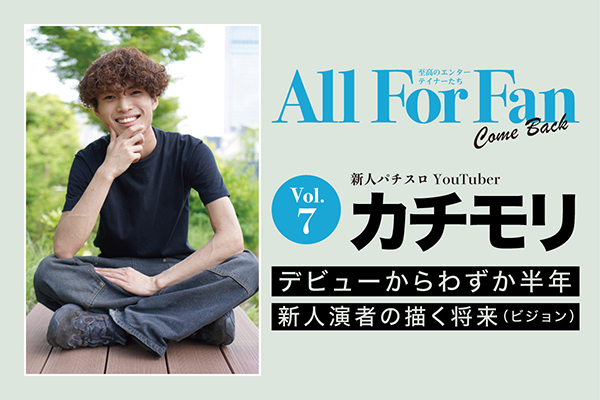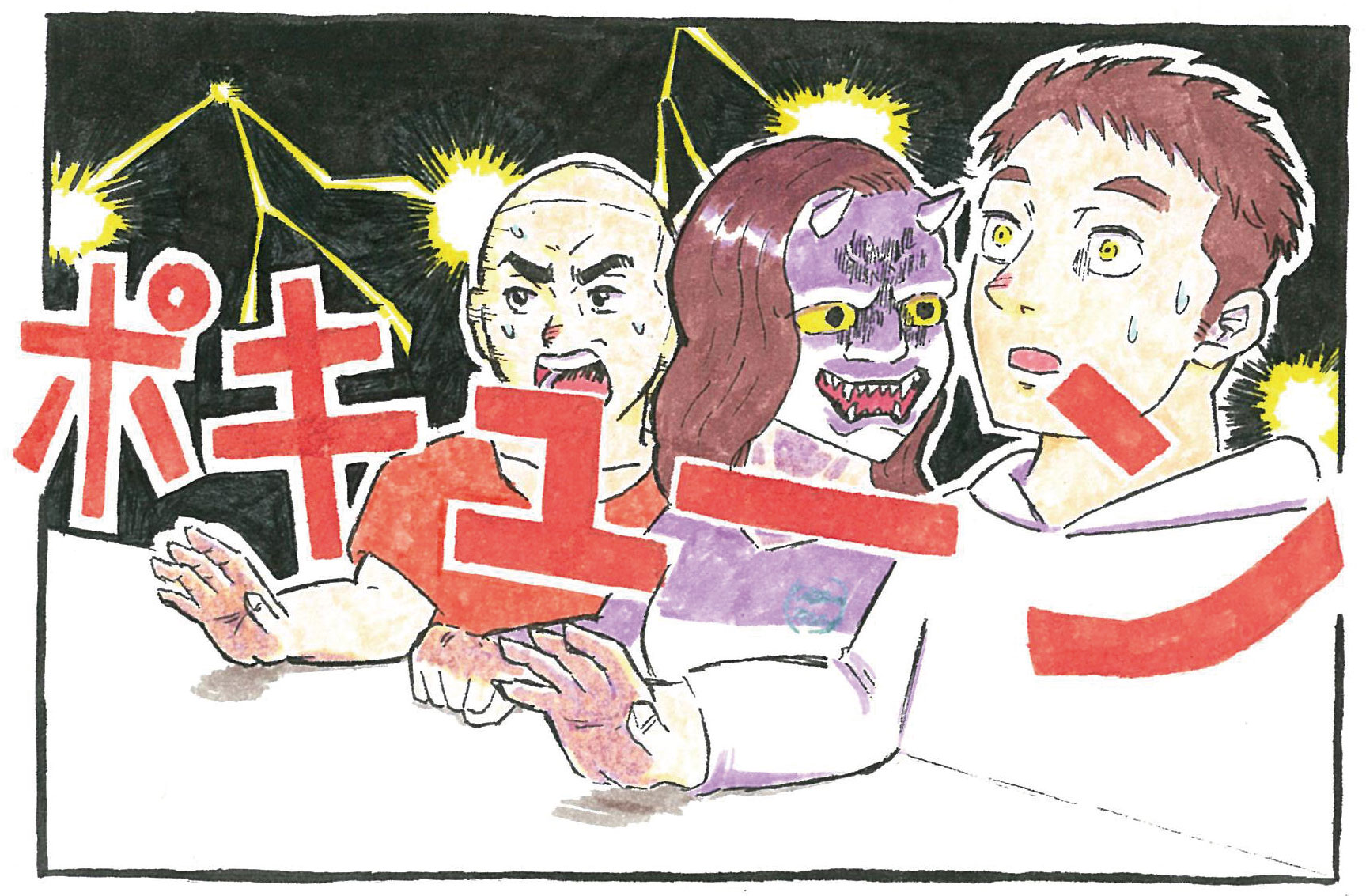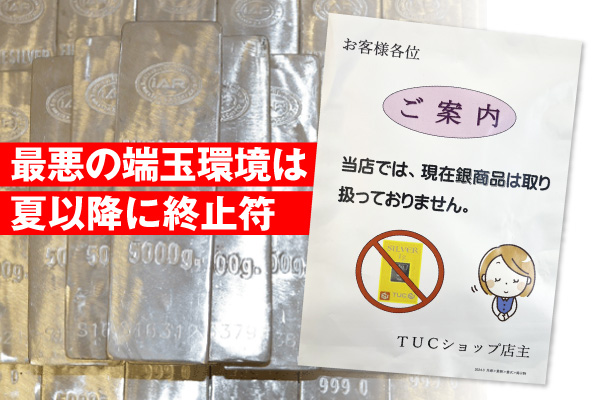ウーバーはフードデリバリーの立役者である反面、配達員は各自個人事業主なので運転マナーや身だしなみなどの悪評が日増しに増えている。
こうした声に呼応したのか、読売新聞と日本マクドナルドは新聞配達網を利用して、マクドナルドデリバリーを行う業務提携を4月28日に発表した。地域を知り尽くしている新聞配達員が丁寧な接客でハンバーガーを宅配することで安心感も届ける狙いがある。

日本マクドナルドは2010年からマッククルーによるデリバリーサービスをスタートさせているが、新聞配達員との協業により、さらなるデリバリー需要の拡大を図る狙いがある、と読んだ。
フードデリバリーはまだまだ拡大するのか、それともコロナが収束したら需要は落ちるのかの経営判断になる。マクドナルドやピザ屋が自社の商品を配達するのは、昔からある出前だが、ウーバーイーツは配車サービスから派生したもので、需要と供給をマッチングさせるところが斬新だった。
躍進目覚ましいウーバーイーツだがインドや韓国市場からはすでに撤退している。いずれも自国内の強力なアプリが浸透していたためである。
同社は事業を展開するすべてのマーケットでシェア1位か2位のプラットフォームになることを最終目標としている。赤字が続きシェアが望めないと判断すると、決断は早い。さっさと事業を売却して撤退するのがこれまでのパターンだ。
フードデリバリー市場も競争相手が増え、ウーバーイーツの配達員の稼ぎも減っている。1年前なら楽に月30万円は稼げていたのが、ライバルが増えて報酬が2~3割カットされたため、「無理して、無理して働いても月に15万円ほどしか稼げなくなった」と嘆く。
ウーバーイーツもコロナ収束後にデリバリー需要が減れば、撤退する可能性がある。その時は買収のチャンスである。
一定のプラットフォームがあり、AIが配達を振り分けるシステムも構築されている。これをホール企業が買収して新規事業としてデリバリーサービスを始めるのも面白い。ホール企業なら会員管理しているので、顧客に対する宅配サービスだってできる。高齢化して顧客は買い物も億劫になっている。買い物代行もできるだろう。
さらにホール企業の強みは、接客教育が徹底されているので、配達先でも不評を買うことはない。
新規事業を探しているホール企業のヒントにはなっただろうか?
 LINE
LINE