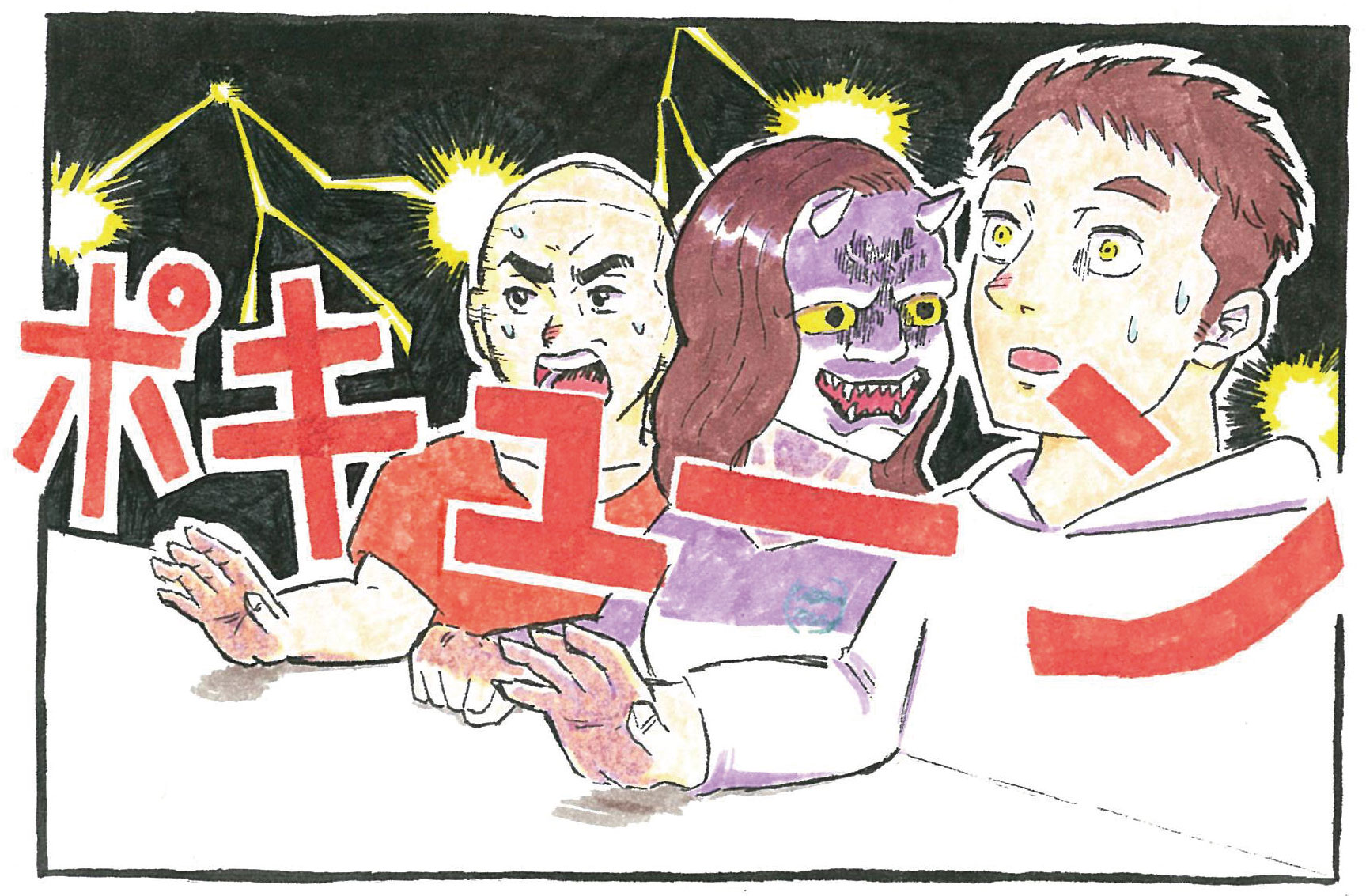フリーライターがライフワークとして昭和、平成で消えた職業を調べている。ある程度のボリュームがまとまれば「日本の絶滅危惧種」(仮題)として出版する計画がある。
色々な業種を当たっている中で、たどり着いたのがパチンコ業界だった。ライターは釘師とパチプロに着目した。ライターがイメージしているのは「釘師サブやん」の世界だ。
あらすじはこうだ。
昭和30年代。渋谷のパチンコ店第一ホールで、茜三郎こと天涯孤独のサブやんは、祖母の遺言を胸に秘め、たったひとりで上京し、パチンコ台の釘の傾きを調整する釘師をしていた。
「釘師の神様」と呼ばれていた根岸佐助に師事し、目指すは日本一の釘師である。そんなある日、パチプロ・美球一心が来店。サブやんが釘を締めて玉を出なくしていたパチンコ台を、秘打正村昇り竜を使って玉1個だけでいとも簡単に攻略していた。これに挑発されたサブやんは、美球一心に金札勝負を挑む。
サブやんはこれがきっかけで、全国のパチプロたちから敵視される存在となり、さまざまな試行錯誤を繰り返して、パチプロやゴト師たちと戦っていく。
ま、これは漫画の世界での出来事だが、実際の釘師とはどういうものだったのか?昭和から平成に代わるころの釘師の姿の一端を紹介しよう。
Aさんはおじが経営するホールで10年ほど釘を叩いていた。その技術を見込まれ、セブン機ブームに沸くH社の技術部準社員となって開店釘を叩くようになる。
5~6年して釘師として独立。ピーク時には22~23店舗の釘を叩いていた。閉店から開店までの限られた時間で、移動時間を含めるとよくこの店舗数を管理していた、と感心させられる。ポイントになる台だけを叩いていたんだろう。
「助手2人を連れて和歌山から大阪の北摂地域までを一晩で回っていました。店が閉店してから明け方まで釘を叩き、それが終われば共同経営していたホールの開店準備です。家に帰るのは昼の2時、3時。こんな生活が5年ほどつづきました。体も壊し体力的にも限界でした」(Aさん)
これらの得意先に機械を販売するために遊技機販社を興す。釘の面倒を見ながら得意先を繁盛させるスタイルには定評があった。Aさんが独自に編み出すゲージは、客付きがいい“Kゲージ”ともいわれ、メーカーからも一目置かれた。
「機械を買ってもらったら終わりではない。機械を入れたい上は、お客を付かせて、店に実績を残してもらうことが私の仕事。釘のことで文句をいわれたら、オーナーでも鍵をつき返していました。それぐらい自分の仕事には自信を持っていました」
一方のパチプロも釘師サブやんに出てくるようなパチプロをライターはイメージしているのだろうが、現実問題、平成になるとパチプロよりもスロプロで生計を立てていたケースの方が多い。
そのスロプロたちも食えなくなってどんどん引退している。それについては日報の「スロプロ歴25年のベテランが引退するわけ」に詳しい。
ちなみに日報の過去記事でこのエントリーが一番読まれている。
 LINE
LINE