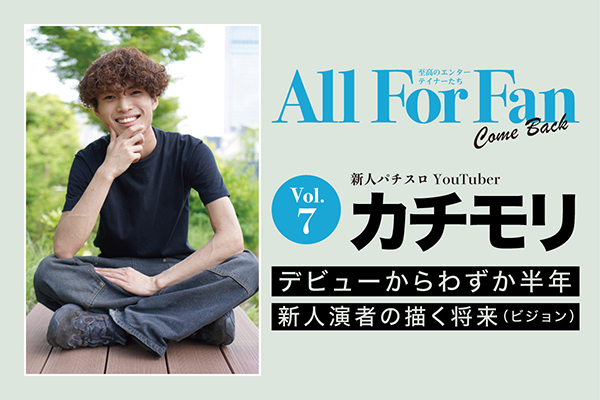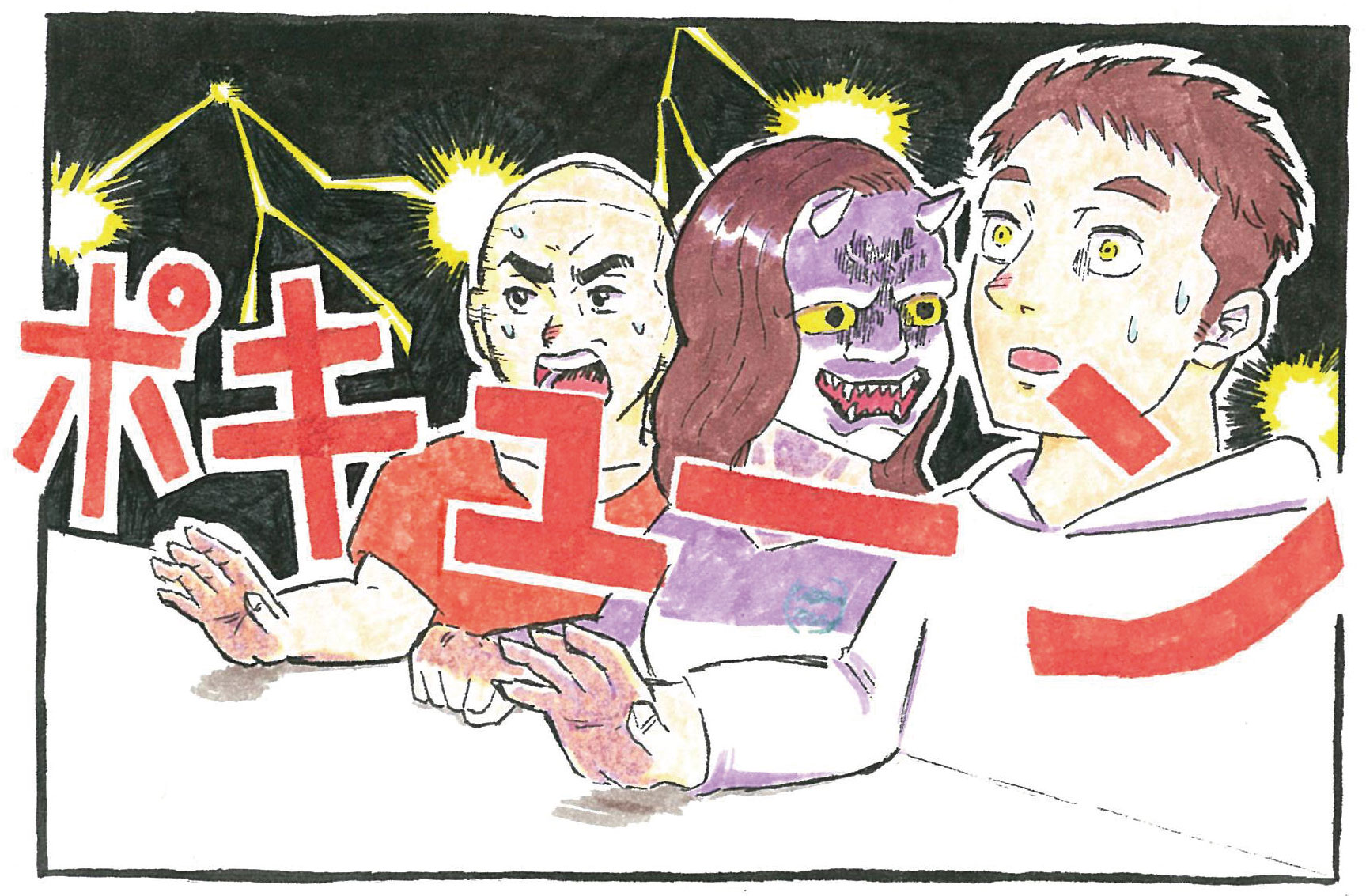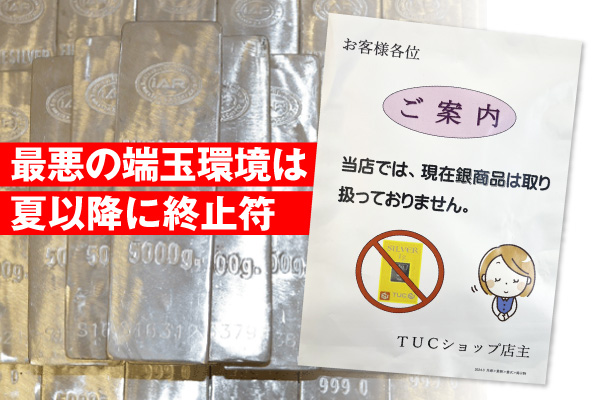コロナ禍で「ノートが売れていない」と話すのは総合商社の関係者だ。
大学はコロナ禍の1年間、オンライン授業が続いている。大半の学生は授業を録音したり、講義内容をスクショで済ませてしまうので、全くノートに取ることがなくなったために、ノートが売れなくなっている、という。
私立の高校の中にもオンライン授業を取り入れているケースがある。同様に録音とスクショが当たり前になってきている。
もちろん、小中学校用のノートは従来通り売れているが、大学生のノート需要が減っている、ということだ。それに伴いコクヨやぺんてるなどの文具メーカーは業績を落としている。
大学生は授業に出席しないで、友達からノートを借りてコピーしていたが、そういう時代も終わった。今や大学は放送大学状態になっているが、授業料の値下げをする気配はない。
関係者の話は続く。
コロナ禍でリモートワークが普及したことで、事務機器のオカムラ(旧岡村製作所)が机や椅子、ロッカー、照明器具、ホワイトボードなどのオフィス用品が売れなくなって困っている、という。リモートワークに伴い、事務所スペースを縮小するところも出てきているわけだから、事務用品にも悪影響が出ている。
政府は企業に対してリモートワーク7割を求めているが、それを実現したら7割のオフィス需要が消えてしまうことを意味する。
コロナはずっと続くわけではないが、生活習慣や商習慣をコロナ禍が一変させたことだけは、厳然と残った。
コロナ禍とは関係ないが、政府は脱炭素社会の実現のために2050年までにガソリン車から電気自動車に切り替える目標を発表している。日本の基幹産業である自動車産業は、電気自動車では世界から一歩出遅れている。自動車産業はすそ野が広いだけに、構造の簡単な電気自動車になると仕事を失う分野も出てくる。
電気自動車になれば戸建て住宅は充電できても、集合住宅ではその整備にも対応が迫られる。しかし、路面に設置した充電器からコードレス充電と言う方法も導入されるようだ。
世の中は激変しているが、パチンコ業界はどうか?
前出の総合商社の関係者はこう指摘する。
「JRAは無観客でもネット投票のお陰で2020年の売り上げは前年比で103%アップした。パチンコの様に規制が厳しい業界は革新が進まないので、時代に追いついて行かない。規制とはミャンマーの民主化を妨げる悪のようなもので、業界が廃れるだけ」
戦後からパチンコは風営法の縛りの中で、射幸心を提供するビジネスモデルを続けてきた。しかし、風営法の枠内では規制が多すぎて技術革新も進まない。パチンコ業法か従来通り風営法で存続するかの議論もあったが、大多数は風営法の枠の中で営業することを選択した。
パチンコ業界にもコードレス充電のような発想が必要だが、それにはパチンコ業法でなければ、未来のシナリオも描けない。
5G世代は始まったばかりだが、10年後には7Gに移行している。リアル店舗へ行かなくても仮想空間でパチンコをするには風営法では無理だ。
風営法で淘汰されたホールが生き残るにはパチンコ業法で前進するしかない?
 LINE
LINE