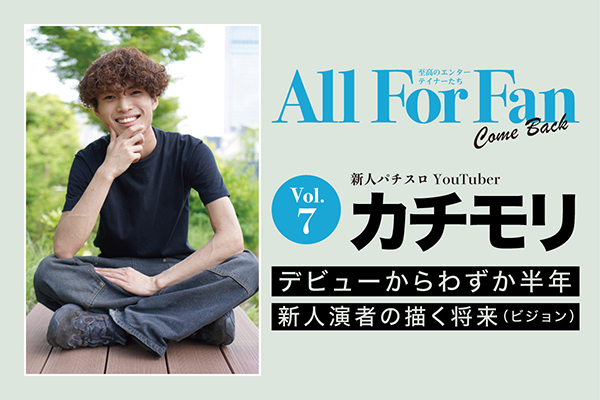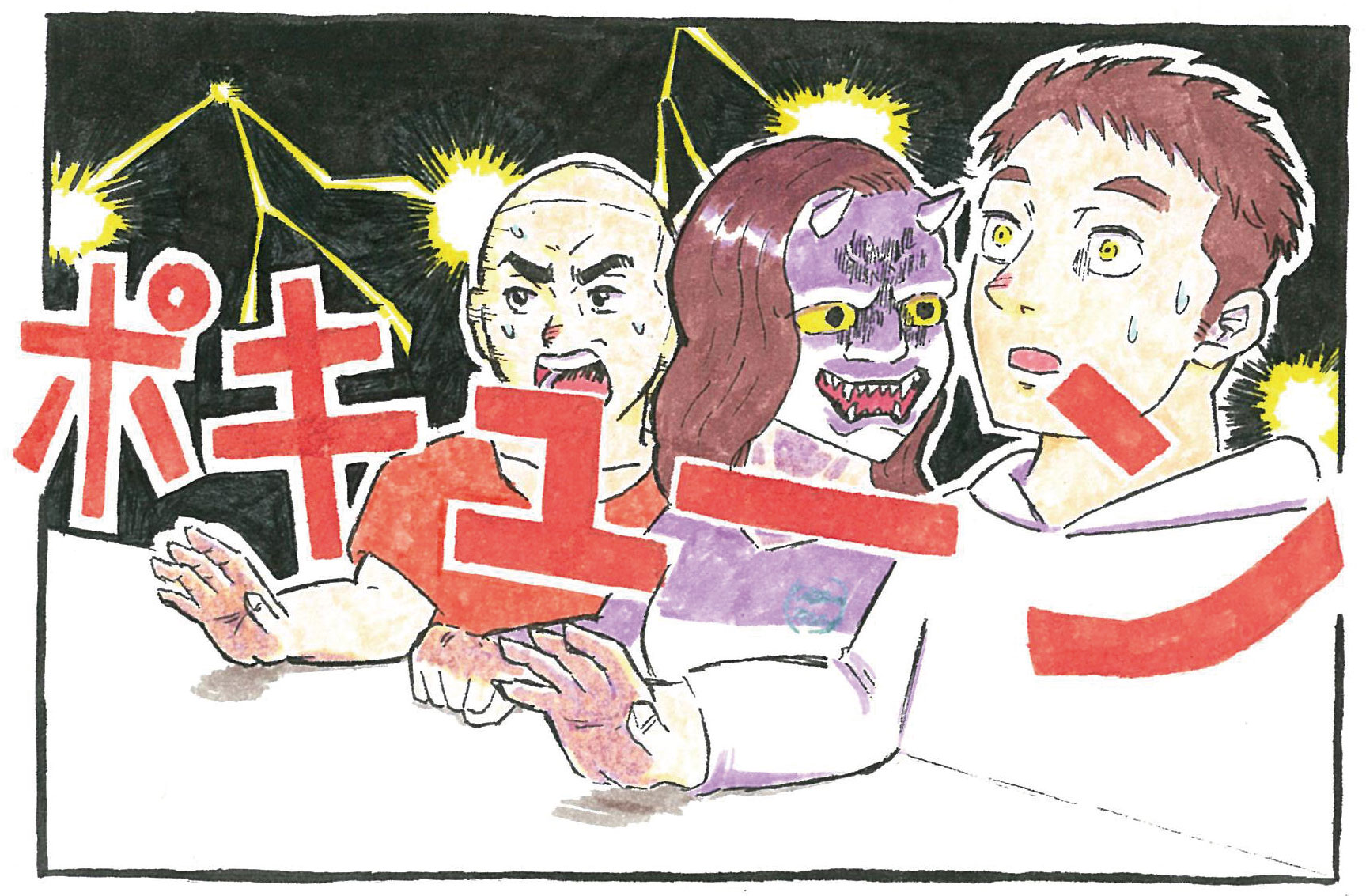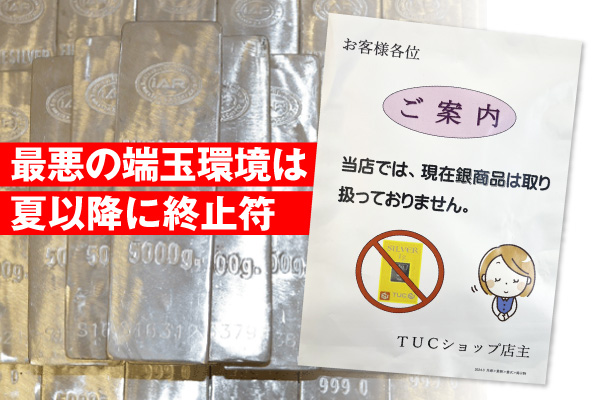本当に顧客ニーズは探れているか?
2020.12.13 / コラム顧客ニーズには、大きく分けて『顕在的な顧客ニーズ』と『潜在的な顧客ニーズ』があり、この2つそれぞれを更に顧客層や顧客タイプに分類して深掘りしていく必要があります。
更に、私たちの商売は『可処分所得と可処分時間』が重要で、顧客層や顧客タイプの生活スタイルや背景も想像して顧客ニーズを探ることになります。
まず、既存顧客の『顕在的な顧客ニーズ』に関しては、4P・1P・20S・5S(2Sなども)・ミドル・ライトミドル・甘・・・・・の、現在使用している機種の稼働状況から、比率で把握していくことで、顧客ニーズを満たすための対象となる機種から、ニーズを満たすための価値を把握することが可能になります。
しかし、データで把握するものは「把握したいもの」しか見えないので、ニーズを満たされないお客様は離反していきます。
次に、ライトユーザーも含めて、これからファンになって欲しい未経験の方や休眠ユーザーの『顕在的な顧客ニーズ』も探る必要があります。
不安に感じていることや興味が湧きそうなことを想像し、ニーズの仮説を顕在化してお店で取組む必要があります。
そして、『潜在的な顧客ニーズ』に関しては、気付いたら顕在的なニーズになるもので、知らなければニーズにはなりません。
ここで注意が必要なことは、まったく新しいニーズだけではなく、【気付いていないお客様にとっては新しいニーズと、それを満たす価値を感じる】というもので、特にライトユーザーのお客様においては知らないことが多いので、既存のニーズを満たす価値をしっかりと伝えることで興味と関心を持ってくれるものもあります。
前回のコラムで、業界の「ちょっと変だな」ということを書きましたが、いろんな設備や機種が出ていますが、『これは顧客ニーズの何を解決して、何を満たすものなのか?』『どんな価値を誰に提供していくものなのか?』という点で疑問に思うものがあります。
私が気付いていないだけで、ファンを増やすための重要な価値提供になっているのであれば、それはしっかりと、「こんなお客様には、これがどんな役に立つのか」という点を、お客様にしっかりと訴求する必要があります。
答えが曖昧なものに関しては、改めて顧客ニーズから考えてみることで、必要か不必要かも判断していけます。
いずれにしても、既存のお客様、これからファンになってほしいお客様に提供できる価値を考えるには、まずは顧客ニーズを常に探り続けることが重要になります。
新台をお店に置いておくだけで、お客様が勝手に価値を見出して台とつながってくれるわけではありません。(これをしてくれるのはごく一部のユーザーのみです)
先日、知り合いの異業種でコンサルタントをしている方が面白い話をしていました。
「顧客ニーズを探る達人はお母さん」
というもので、お母さんは言葉も発しない、明確な意思表示もできない赤ちゃんが求めていることを想像して、あれこれ探りながら赤ちゃんを育てていきます。
毎日、赤ちゃんのニーズを探ることで、何を求めているのかの精度が高まっていくという話です。
なるほど!と思ったのは、『対象のお客様にしっかりと心を寄せてニーズを探る・対象のお客様になりきってニーズを探る』ことを普段から繰り返さないと、提供する価値の精度は高まらないし、相手が求めていることを満たす価値ある商品やサービスも提供できないというものです。
機種データでは、お客様の支持している状況は分かりますが、『どんな価値を支持しているのか』をしっかりと探っていく必要があります。
ついつい、「この機種が好きな人は、こんなことを求めている」と思い込んでしまいますが、それは本当に顧客ニーズにあった検証なのか?を実際のデータからでは振り返り、お店の活動に関してはニーズを満たす価値を考え続けて提供することがファンで居続けてもらうことにおいて実施すべきことです。
本当に顧客ニーズを探れているのか?私自身も常に問いかけていこうと思います。
 LINE
LINE