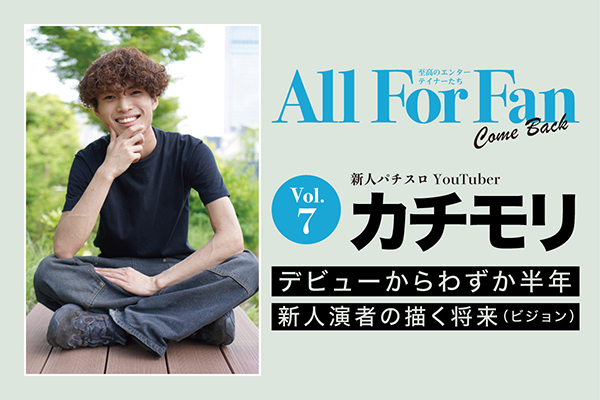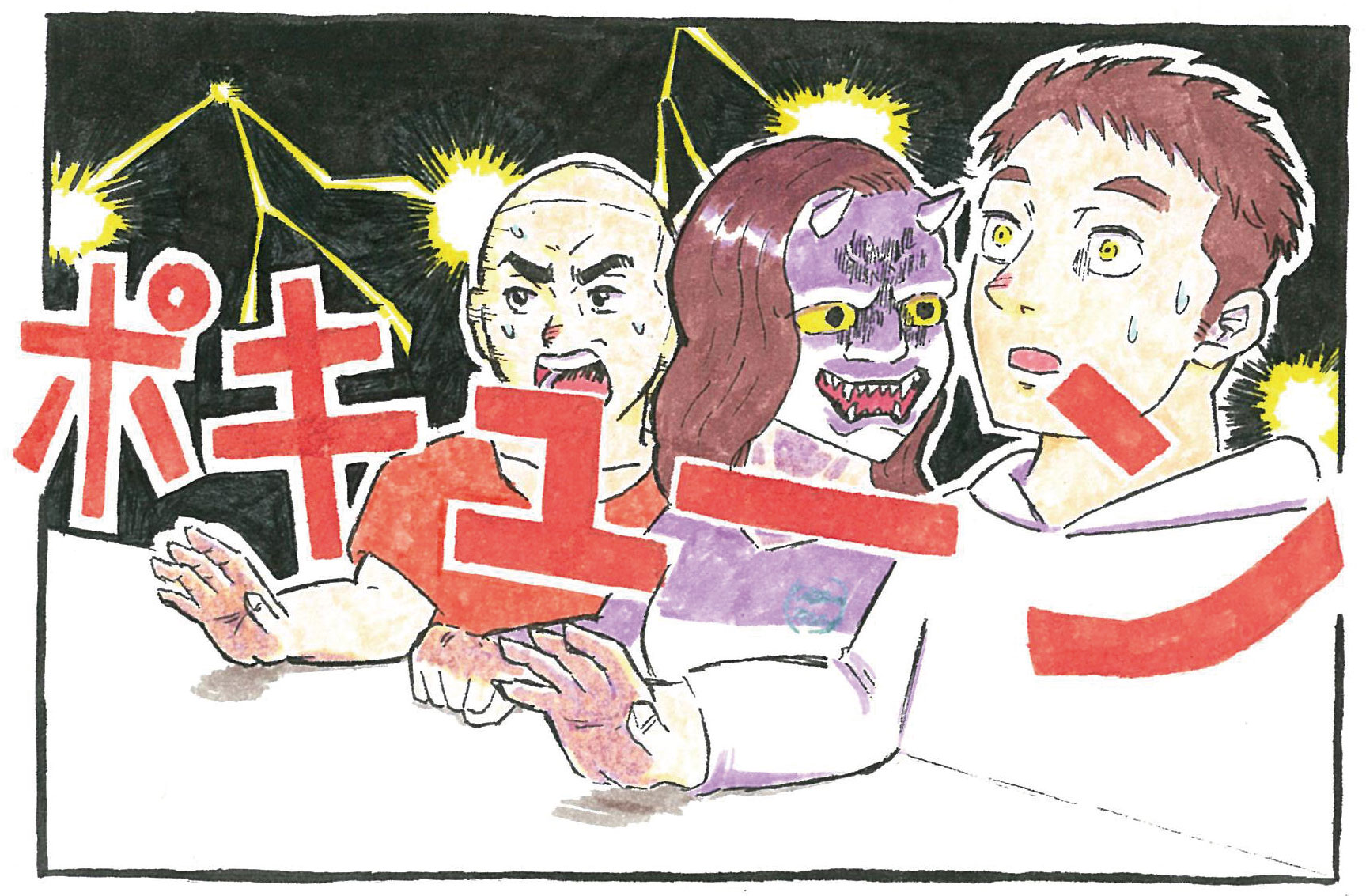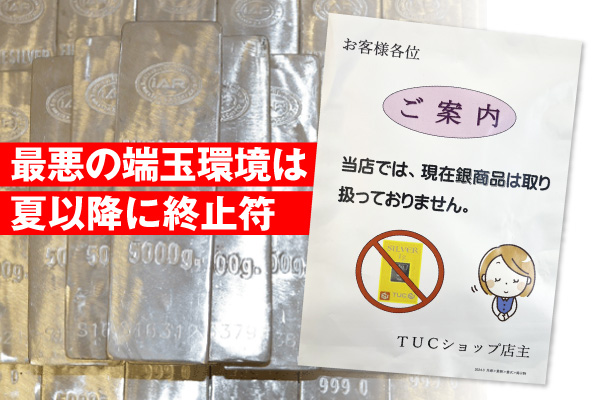出でよ、業界を改革する辣腕経営者
2020.11.25 / コラム「異業種企業によるパチンコ業界への参入実態」(鍛冶博之著)というタイトルの研究論文がある。2007年に発表され、ホールの経営改革に異業種がどういう影響を及ぼしたかを考察する内容だ。
結論から言うと異業種参入組はほとんどがホール経営から撤退しており、業界を変革する力にはなり得なかった…。
1980年代後半、パチンコ業界へ三菱商事や住友商事という日本屈指の一流商社がプリペイドカード事業で参入したことが、異業種からのホール経営参入の呼び水にもなった側面もある。
当時はバブル経済が崩壊した直後。不況から脱出するために異業種企業は、不景気にも関係なく発展し続けるパチンコ業界に熱い視線を送るようになる。
1988年にはパチンコメーカーの平和が業界初の株式上場も果たしていた。東京の買い場からは暴力団を締め出し、1992年には暴対法も施行され、パチンコ業界の健全化が促進される。異業種の“不安”を払拭する手助けにもなった。
流通系では西友の「シンフォニー」、ダイエーの「パンドラ」、信販系ではクレディセゾンの「コンサートホール」、交通系では神奈川中央交通の「スクランブル」、琵琶湖汽船の「くずは会館」、神姫バスの「ニューしんき」などが子会社を通じでホール経営に参入した。
流通系が参入した背景には低価格化によって収益が悪化したことなどから業態転換が迫られていた。ショッピングとパチンコを含めたアミューズメント施設の複合化で集客効果を高めようとした。一方の交通系は遊休地の有効活用という狙いがあった。
流通系の知名度が高い企業がホール経営に参入することで期待されたのは次の通り。
① 業界のイメージアップ
② 流通業の主要客層である女性客の取り込み
③ 大手企業参入による安心感
④ 景品に季節商品を取り入れ新たなパチンコの魅力発信
⑤ これらが融合してパチンコファンの増加
などが挙げられた。
しかし、異業種参入は1998年以降はピタリと止まった。郷に入れば郷に従え。異業種がホール経営改革に乗り出すようなこともなかった。なぜなら、異業種参入は最初から業界の健全化を促進することが目的でもなく、利益を追求した多角化戦略の一つであったことや、不採算部門や遊休地の有効活用が目的だったからだ。
既存ホール企業の脅威になることもかった。そりゃそうだろう。一世はヤクザと渡り合い、店を守った。酸い味甘いも噛み分け、猥雑な業界を一瞬の判断でGOサインを出すホールオーナーに、“業界素人”のサラリーマン社長が太刀打ちできる業界ではなかった。
異業種の呼び水となった三菱商事はカードの偽造問題で怨念を残しながら業界から撤退していった。
射幸心を制する者がパチンコ業界を制する。異業種参入による業界再編は起こることもなく、今を迎えている。
業界を変えるのは異業種の大手企業ではない。一代で1兆円企業を作り上げるような辣腕経営者が、本気になって業界に参入した時に業界は変わる。
 LINE
LINE