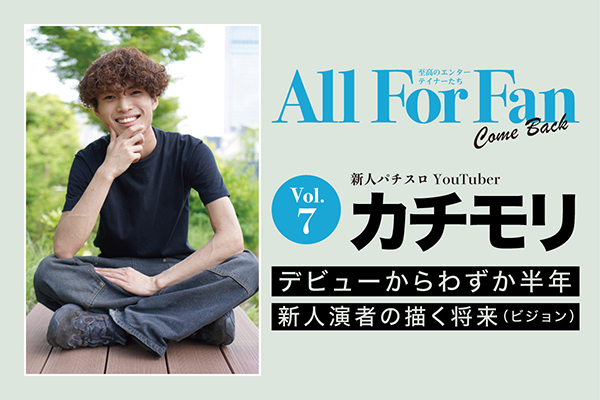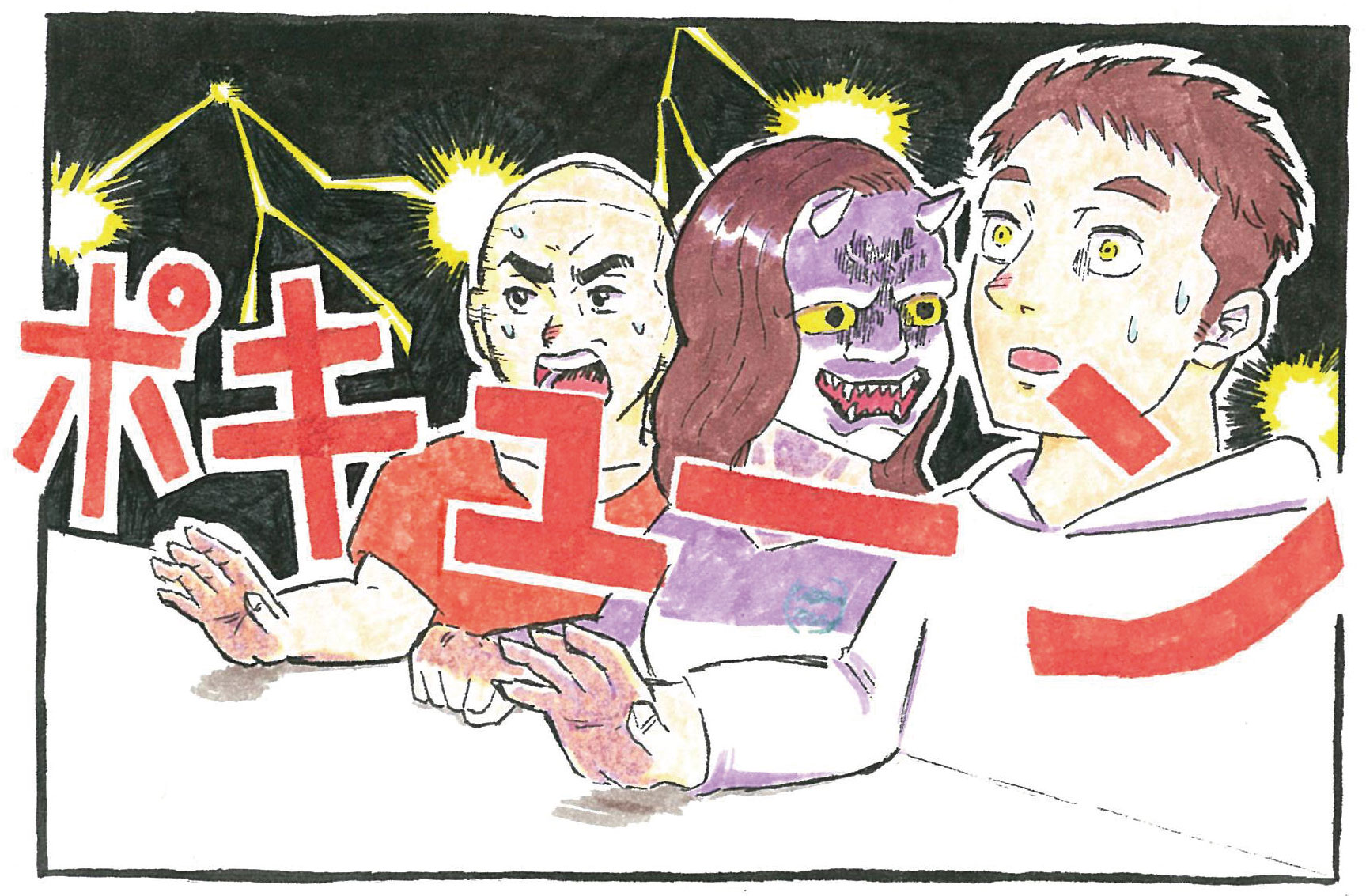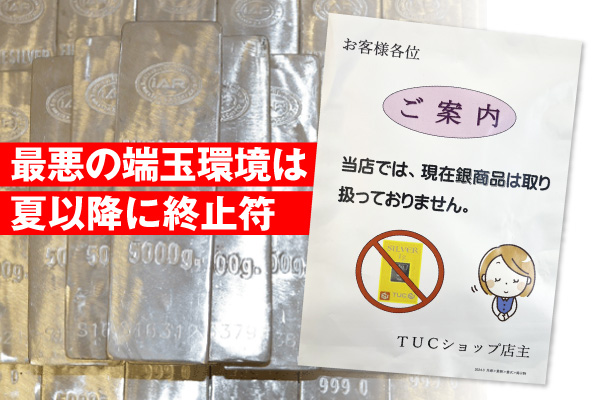年々遊技機市場が縮小する中でメーカーが採っている手段が、機械代を値上げすることで売り上げを維持することだ。販売台数が減っても値上げ分で売り上げを保とうとしている。
遊技機市場と同様に毎年値上げすることで、売り上げを維持・拡大するそっくりな市場がもう一つあった。
それがランドセル市場だ。
少子化問題で年々子供の数は減っている。例えば下記のグラフのように1992年には小学1年生の数は約140万人いたのが、2019年度は約100万人まで減少している。27年間で40万人減っている、ということはランドセル市場もそれだけ縮小している、ということだ。

しかし、少子化問題もなんのその。右肩上がりで売り上げを伸ばしているのがランドセル市場なのである。
で、ランドセル市場をけん引するのがセイバンとイオンである。この2社がランドセル市場の60%を寡占する(両社ともに30%ずつのシェア)。
「値段の付け方がパチンコとそっくりです。来年は100万個市場を切ってついに90万個台に突入しますが、ランドセルの平均価格も4万円→4万3000円と値上げしていき、今は4万9000円です。各社とも高いランドセルをいかに買わせるかに知恵を絞っていますが、高級品になれば7万円台のものもあります」(ランドセル担当バイヤー)
特に後発組ながらランドセル市場で成功を収めているのがイオンだ。ランドセルと言えば、男の子は黒、女の子は赤しかなかった。イオンは多色展開で殴り込みをかけトップメーカーと肩を並べるまでに躍進した。小さいメーカーは多色展開すると在庫として余ってしまうので、それができなかった。
セイバンも天使の羽で軽く背負える機能でイオンを迎え撃つ。
「ランドセル市場は500~600億円で推移しています。販売数が減っても機能(スマホ、GPS入れ、防犯ベル、A4サイズ収納)を付加して値上げで売り上げを維持しているのがランドセル。ランドセルは少子化で今の4万9000円から5万5000円が今後の攻防となります。いかにおカネを出させるかは、親やおじいちゃんの心理、つまり入学する子供に恥ずかしい思いをさせたくない、という心理を突く。だから、高いと満足する商品になっているのがランドセルです。制服のお下がりはあってもランドセルのお下がりはない。これはイジメの対象にもなるからです」(同)
高いものが売れるのは日本の恥の文化のお陰でもある。子供や孫に安物のランドセルで恥ずかしい思いをさせたくない。そこに新たな機能を付加して値段を上げていく。
ランドセル担当バイヤーが注視しているパチンコメーカーの機械代の値上げもいずれ限界が来る、と読んでいる。当然、ランドセルも未来永劫値上げを続けられるものでもない。そういう意味で反面教師として業界を注視している。
逆にメーカーはランドセル業界を参考にして今後の販売戦略を練り直すのもいい。
 LINE
LINE