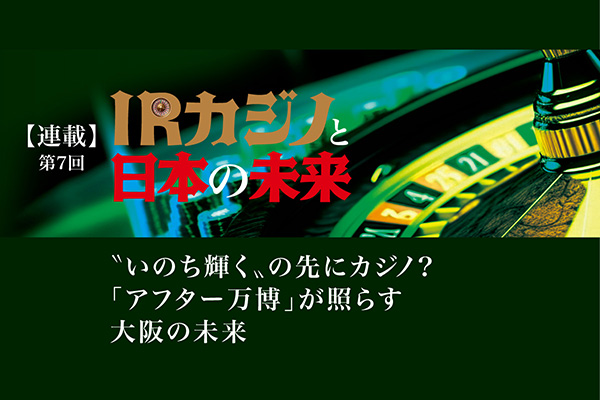〝いのち輝く〟の先にカジノ? 「アフター万博」が照らす大阪の未来
2025.11.23 / カジノ2025年10月13日、大阪・夢洲で開催された大阪・関西万博が閉幕した。
華やかな演出と「いのち輝く未来社会のデザイン」という壮大なテーマのもと、多くの来場者を集めたこのイベントに対し、主催者や関係者は「大成功だった」と胸を張る。だが、その〝成功〟の定義は妥当なのか。数字の裏側にある構造と、すでに進行する「アフター万博」への懸念を掘り下げる。
来場者数は本当に成功の証か?
万博協会によれば、閉幕時点での入場券販売枚数は2200万枚を突破し、計画の1800万枚を大きく上回った。SNSなどでの評判も相まって、入場者は日を追って増えていった。
しかし、実態に目を向ければ、来場者の約67%が近畿圏からの訪問であることが明らかになっている(エリア別来場者構成図より)。関東(16.4%)や中部(8.7%)を加えると国内客が93.9%を占め、海外からの訪問者は6.1%にとどまった(図1)。

つまり、万博が掲げた「国際博覧会」としての体裁とは裏腹に、実態は〝地元イベント〟の色彩が濃い。さらには、複数回訪問したユーザーも多く、実際のユニーク来場者数は公表されていない。
入場券枚数=延べ来場数であるなら、実際には一人が3回、4回と足を運んでいる可能性もある(ちなみに在阪の知人は複数回パスで20回来場したという)。
真の動員力はどうだったのか、その内実はあいまいなままだ。
黒字という数字のマジック
関係者が声高に「成功」を語る根拠のひとつが、230〜280億円とされる運営費の黒字見込みだ。計画では、969億円を入場券売上で賄う予定だったが、想定を超えるチケット販売(+200億円)と、グッズ・飲食収入(+30億円)が黒字に大きく貢献した。さらには支出も抑制され、50億円程度のコスト削減が見込まれている(図2)。
特に注目すべきは「公式グッズ」の売上である。万博協会の関係者によれば、関連グッズの総売上は8月末で800億円を突破したとも報じられており、この数字は過去の万博や大型イベントと比しても異例の規模だ。
だが、実際の運営主体の収入はその一部(例えば6%程度のロイヤルティー)である上、物販収入がどこにどのように分配されているかも不透明である。中小の出店者にどれだけ利益があったのか、あるいは大手広告代理店やイベント企業がどの程度の取り分を得ているのか。こうした経済効果の分配構造は表に出てこない。
加えて、この黒字はあくまで「運営費」であり、2350億円にのぼる建設費や、250億円の警備費は含まれていない。建設費は国や大阪府・市、経済界が負担し、警備費は国の持ち出しだ。会場の整備・警備に税金が使われた事実を前に、この黒字は一種の数字のトリックと見ることもできる。協会の財務責任者自身が「250億円以上の黒字でないと本当の黒字とは言えない」と語っているのも印象的だ(図3)。

不透明な意思決定とアフター万博
ともあれ万博は終わった。解体工事が始まった隣接地では、すでに「カジノを中核とする統合型リゾート(IR)」の整備が本格化している。万博跡地には高級ホテル、サーキット、世界最大級のプールなど、豪華なエンタメ空間の構想も打ち出されているが、そこに市民の声が反映されているかは疑問だ。
夢洲の再開発は住民投票などのプロセスを経ておらず、決定はトップダウンで進んでいる。現地に足を運ぶと、IR予定地の建設工事はすでに着工され、大型のクレーンが林立し、稼働を始めていた。予定地には「大阪IR」とバンパーに表示されたトラックが引っ切りなしに入ってくる。そこには〝万博成功〟の勢いに乗じて、地元住民や市民団体の懸念の声もかき消されるかのようだ。
IRの建設をめぐっては、大手ゼネコン、広告代理店、観光業界、さらには海外IR運営企業との連携といった、複雑な利害構造が交錯している。とりわけMGMリゾーツ・インターナショナルとオリックスによる運営体制は、アメリカ型カジノビジネスの強い影響を示しており、外資による収益構造と地元への還元のバランスにも注視が必要である。
万博は「誰のエンタメ都市」だったのか?
万博閉幕後の都市構想において、大阪府は「アジアNo.1のエンタメ都市」を掲げている。しかしこの「エンタメ」が誰に向けたものであるかは、極めてあいまいだ。IRやカジノという形での成長戦略は、必ずしも全市民の利益に資するものではなく、むしろ格差や社会問題の拡大をもたらすリスクをはらむ。
さらに、関連企業の影も見え隠れしており、ギャンブル産業との接続が強く意識される構造も見て取れる。かつて「万博の理念は持続可能性と健康・安全」と高らかに掲げたのとは対照的に、ポスト万博の都市像はギャンブルと消費の色濃い空間へとシフトしている。
230億〜280億円の黒字が確定するのは2028年3月以降とされ、その使い道については関係者や有識者による検討が予定されている。吉村洋文・大阪府知事は「黒字をリング維持に充てられないか」と提案している。だが、工事費の未払い問題やパビリオン撤去費の議論もあり、最終的な「レガシー」のあり方には不透明感が漂う。
過去の愛・地球博(2005年)の黒字139億円は研究機関の支援や名古屋城復元に、1970年の大阪万博の黒字194億円は文化事業に使われた。対して、今回の黒字が維持管理や法的トラブルの穴埋めに終始するなら、「レガシー」は幻に終わる可能性すらある。

①/閉幕後の大阪・関西万博の思い出に浸りながらフェンス越しに入場ゲートを名残推しそうに撮影する地元のファンたち。②と③/万博の象徴「大屋根リング」を背景に、IRカジノ建設の工事現場にはひっきりなしに「ゆめしま 大阪IR(株)」の表示を掲げた大型トラックが資材を搬入する。現在、躯体工事が始まり、2030年秋ごろの開業を目指す。
 LINE
LINE