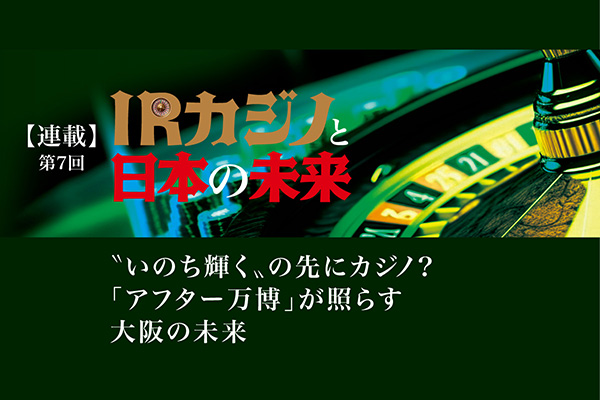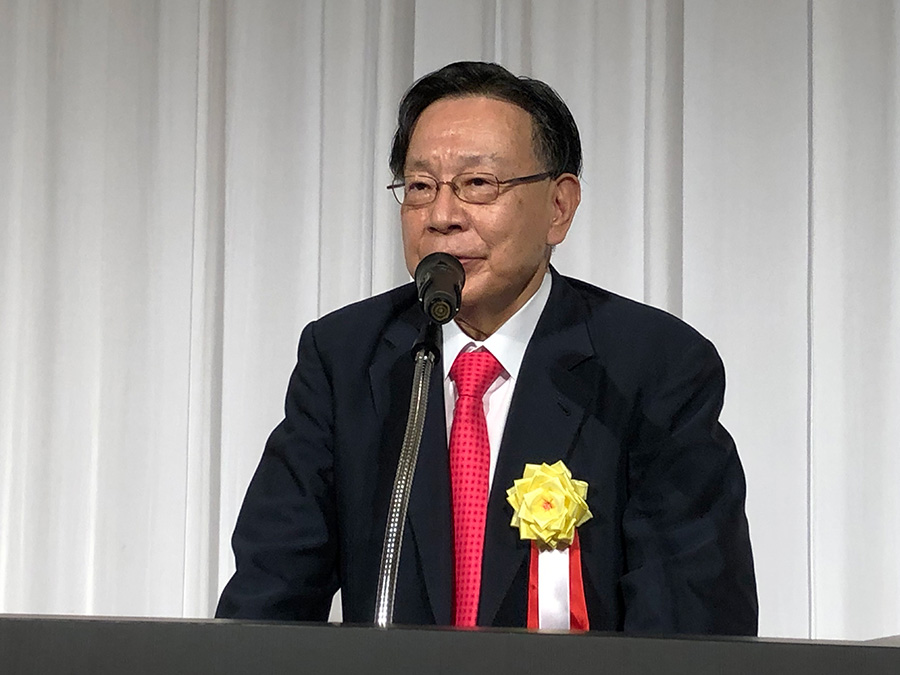カジノ誘致レース〝再び〟 次の候補地に のしかかる負のリスク
2025.10.10 / カジノ2025年春、統合型リゾート(IR)の第1号案件である「MGM大阪」が本格的な着工に踏み切った。舞台となるのは、大阪・関西万博と同じく夢洲(ゆめしま)という人工島。日本初のIRとして2030年の開業を目指すこのプロジェクトは、政府が掲げる「観光立国」政策の象徴であり、いよいよ現実味を帯びた国家的事業である。
大阪IR着工の陰で、第2次IR誘致の動きが水面下で再び進み始めている。国は2027年末までに、最大2件のIRプロジェクトを追加承認する可能性を示唆しており、各地の自治体や経済界ではその是非をめぐる議論が再燃しつつある。
だが、誘致レースの先に待つのは、夢洲が象徴するような、経済効果とリスクが錯綜する複雑な現実である。政府や推進派が強調するバラ色の未来とは裏腹に、そこには住民訴訟、地盤問題、巨額の公費投入、そしてギャンブル依存症という構造的な課題がのしかかっている。
起工式の祝祭の裏で
2025年4月24日、万博会場の北側に隣接するIR予定地(約49ha)の一角で大阪IR建築工事の着手と起工式が行われた。
出席したのは大阪府知事の吉村洋文氏、大阪市長の横山英幸氏をはじめ、事業関係者150人。吉村知事は「IRは圧倒的な非日常空間を生み出す。観光やビジネスの新たな需要を創出し、大阪の経済成長をけん引する起爆剤となる」と強調。
続いて横山市長は「1兆円超の投資が行われ、年間2000万人が訪れる国際観光拠点となる。ベイエリア全体のまちづくりと一体で、未来の大阪を形づくる柱にしたい」と意気込んだ。「年間2000万人」「経済効果1兆円」といった景気の良い言葉とともに、金屏風の前で地酒による鏡開きが行われた。
大阪IRの設計図は豪華絢爛だ。カジノ、ホテル3棟(2500室)、国際会議場、展示場、スパ、劇場など、非日常空間が広がる。事業は米MGMリゾーツとオリックスなどが出資する「大阪IR株式会社」が担う。
しかしこの光景の裏で、複数の住民訴訟が進行中であることは、あまり報じられていない。
住民が問う「公費負担」の妥当性
夢洲はもともと、廃棄物処分場として造成された人工島だ。液状化や軟弱地盤の問題を抱え、大阪市は整備費として最大788億円を負担。さらに将来的な拡張に備え、追加で約257億円が必要になる可能性も示されている。
この公費投入に対し、市民が2022年に大阪市を提訴。IR事業者に貸与される土地の賃料が「安すぎる」として契約差し止め訴訟も起きている。
「今後も税金が使われ続ければ、本来福祉や教育に充てるべき財源が枯渇してしまう」― 原告の一人はそう訴える。
また、大阪市が当初「民設民営」としていたIR構想が、実際には市が多額の支出を行う「準公設型」へと変質している点も問題視されている。
アクセスとインフラに潜む「脆弱性」
夢洲のもう一つの問題は、アクセス手段の限界だ。
夢洲へのメインルートは夢咲トンネルを経由する地下鉄であり、それ以外の代替ルートは少ない。万博開幕初日には地下鉄が大混雑し、最寄り駅がパンク寸前になった。さらに、8月13日の夜に発生した閉園間近の地下鉄のトラブルにより約4万人が一時足止めをくらった。30度に近い熱帯夜の中、〝陸の孤島〟と化した会場内で多くの人たちが一夜を過ごすことになった。
IR開業時にも同様の混乱が予想され、特に災害時の陸の孤島の安全性については「世界中の来場者の命に関わる」という懸念は拭いきれない。
加えて、建設地の軟弱地盤問題も深刻だ。過去には関西空港や万博会場で地盤沈下が発生し、多額の追加費用が発生している。IRでも同様のリスクがあると専門家らは警鐘を鳴らしている。

大阪・関西万博会場から見たIR予定現場の現状(イメージ図)
期待される「経済効果」の不確実性
大阪府・市が掲げる収支計画では、年間1060億円の収益を想定し、そのうち約8割がカジノからの売上とされている。しかし、この試算にも疑問符がつく。
コロナ禍以降、日本国内ではオンラインカジノ(オンカジ)の利用が急増。多くの利用者がスマホでアクセスし、規制が追いつかない中、リアルカジノの集客に影響が出る可能性がある。これについては本連載でも何度か触れてきたように昨今、国によるオンカジ事案の摘発と規制強化の動きが目まぐるしい。もちろんこれはリアルカジノ開業へ向けた環境整備に他ならない。
また、IRの経済効果の大部分が海外IR事業者に流れる構造も批判されている。実際、MGMのような外資系企業が主導することで、日本人客の賭け金が日本国内ではなく企業本国へと還流することが懸念されている。
ギャンブル依存症という構造的リスク
依存問題対策の点でも課題は多い。
大阪府・市はIRによるギャンブル依存症の増加を見越し、「大阪依存症センター(仮称)」の設立を計画している。しかし、その実現性については現場の支援団体からも厳しい意見が出ている。
「具体的な施設像も決まらず、現場にノウハウもない。依存症患者を受け入れられる医療体制すら整っていないのが実情だ」― 公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」代表の田中紀子氏はそう警鐘を鳴らしている。
依存症対策の人材育成には年単位の時間がかかり、拠点施設の立ち上げにはマンパワーも資金も必要だ。だが、行政からの具体的なアクションや協働の姿勢はまだ見えてはこない。
「誘致するか否か」の前に問うべき視点
第2次IR誘致レースは、今後の数年間で全国の自治体を巻き込んで再燃するだろう。
第一ラウンドで応募したが承認されなかった長崎、誘致に前向きな苫小牧市の新市長・金沢俊氏や経済連合会の支持を受けている北海道。一度は応募を断念した和歌山も再び前向きに検討しているという。
そうした中で、MGM大阪が私たちに突きつけているのは、喧伝される「成功モデル」ではない。
それはむしろ、誘致がもたらす制度的な不安定さ、住民との軋轢、公費支出の重圧、そして倫理的・医療的な未整備なまま突き進む構造的リスクそのものである。
「誘致する/しない」の二元論を超えて、今一度問うべきは、「その場所にとって本当に必要な未来像とは何か」である。
その問いから逃げたままでは、次に選ばれる候補地もまた、“負の遺産”への入り口になる危険性がある。
 LINE
LINE