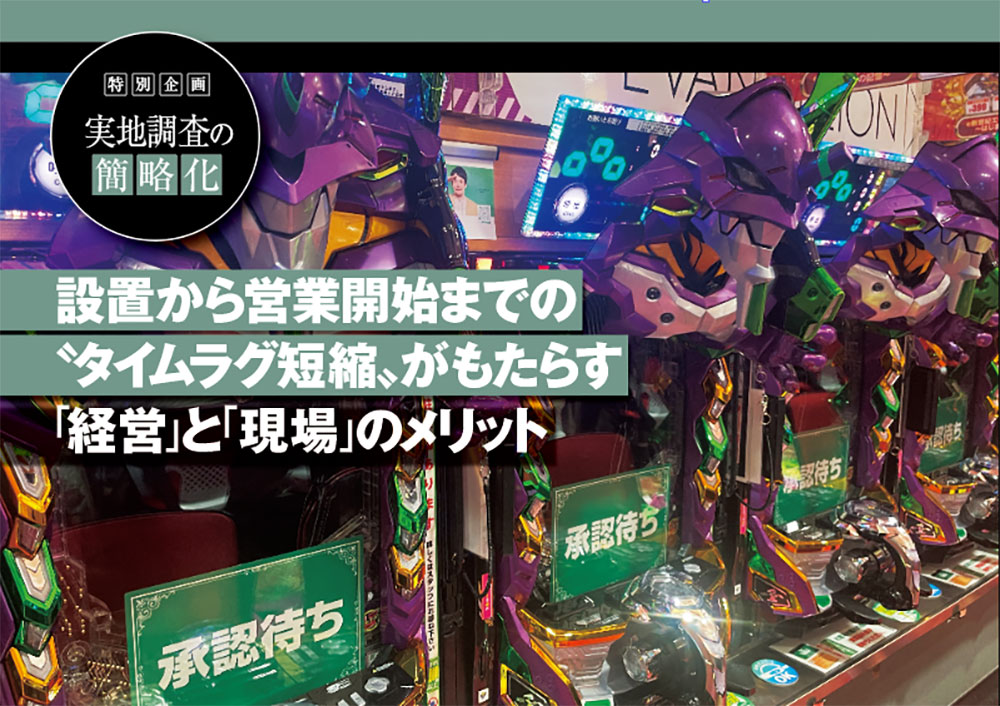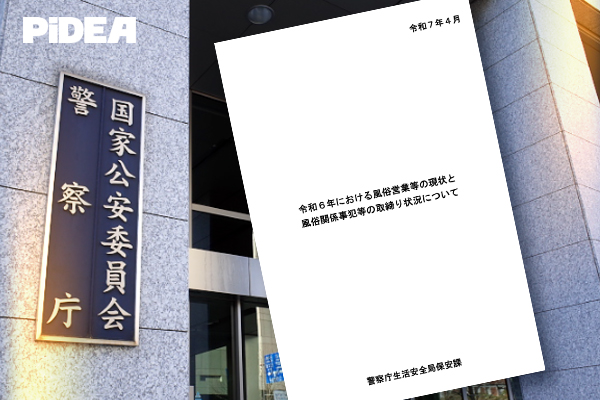津村課長補佐講話「依存防止対策」など4項目を/余暇進
2017.11.15 / ホール11月14日、余暇環境整備推進協議会(略称.余暇進、笠井聰夫代表理事)はホテルインターコンチネンタル東京ベイ(東京都港区)で、平成29年度秋季セミナーを開催した。 同セミナーでは警察庁生活安全局保安課の津村優介課長補佐が「ぱちんこ営業の健全化を進めていく上で特に必要なこと」として4項目について講話した。以下、抜粋、要約。
【ぱちんこへの依存防止対策について】
今回の規則改正により、来年2月1日以降は改正規則に適合しない遊技機は設置することができなくなる。ただし、現行基準による認定を受けた遊技機または検定を受けた遊技機については、当該遊技機の有効期間が満了するまでは設置が認められる。認定申請等に関する事務処理を滞りなく進めるため、都道府県警察と必要な調整を適切に行ってほしい。
また現在、業界においてぱちんこへの依存防止に資する各種取組が進められているところ、今回の改正で営業所の管理者の業務に依存防止対策が追加されることによって、営業所で行われている各種の自主的な取組が管理者の業務として位置付けられることとなる。 営業所の管理者は、 ・ ぱちんこへの依存問題の電話相談機関である、リカバリーサポート・ネットワークの営業所内外における周知 ・ ぱちんこ店の顧客会員システムを活用した自己申告プログラムの導入 ・ 過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施 ・ 18歳未満の者の営業所立入禁止の徹底など、
【射幸性の抑制に向けた取組について】
本年5月、業界が自主的に実施を決めた新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所がいまだ存在していること、また「特に高い射幸性を有すると区分した遊技機」の撤去が進んでいないことは大きな問題であると指摘した上で、6団体において改めてこの課題に対する対応を検討し、その結果を報告するよう要請した。
現在の目標値設定は、来月1日までとなっているが、今後は来月1日以降における新基準に該当しない遊技機、とりわけ「特に高い射幸性を有すると区分した遊技機」の削減に向けた業界の自主的な取組を早期に決定していただきたい。また、こうした経緯も踏まえて、すべての営業所が来月1日の削減目標値を確実に達成していただきたい。
【遊技機の不正改造の絶無】
遊技機の不正改造の絶無について遊技機の流通における業務の健全化悪質巧妙化する事案に対しぱちんこ営業者、遊技機製造業者という垣根を取り払い、事案の情報共有や有効な防止対策を業界全体で模索し、効果的な施策を推進してほしい。また、一般社団法人遊技産業健全化推進機構の活動に対する業界の理解を深めるとともに、その活動を支援するなど、不正改造の根絶を目指す気運を高めていただきたい。
【遊技機の流通における業務の健全化】
昨年4月以降に販売された型式の遊技機については、部品交換の際、変更承認申請に係る保証書の担保として、遊技機の状態が検定機と同一かどうかの点検確認を遊技機製造業者などが一台一台実施することとなった。
また、 遊技機の営業所への設置時や部品交換時に行う遊技くぎの点検確認は、今年4月以降に新台として設置されるぱちんこ遊技機からは目視による確認の補助として「くぎ確認シート」などの器具が使用されていると承知している。こうした取組により確認の精度も向上し、遊技機流通の健全化も進むものと考えている。今後、運用を通じてさらに改善を進めていただくようお願いしたい。
また、要約ではなく正確に内容を把握したい方は、ぜひとも以下の全文をお読みいただきたい。
==========
ただいま御紹介にあずかりました警察庁保安課課長補佐の津村です。
本日は、一般社団法人余暇環境整備推進協議会の平成29年度秋季セミナーにお招きいただき、ありがとうございます。また、業界の皆様には、平素から、警察行政の各般にわたり、深い御理解と御協力を賜っていることに対しまして、この場をお借りして御礼申し上げます。
さて、本日は、ぱちんこ営業の健全化を進めていく上で特に必要であると考えることを何点かお話ししたいと思います。
最初に、ぱちんこへの依存防止対策についてお話しします。
ぱちんこへの依存問題については、昨年12月に成立したいわゆるIR推進法の審議において重大な問題として指摘されたほか、同法の附帯決議において、「カジノにとどまらず、他のギャンブル・遊技等に起因する依存症を含め、ギャンブル等依存症対策に関する国の取組を抜本的に強化するため」、「関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化すること」とされるなど、ぱちんこを含めたギャンブル等依存症への対策の強化が求められました。
こうした動きを受けて、昨年12月に開催されたギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議においては、「幅広くギャンブル等依存症全般について、政府一体となって包括的な対策を推進する」とされ、本年3月、同会議において、「ギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理」が決定されました。
論点整理においては、「出玉規制の基準等の見直し」、「営業所の管理者の業務として依存症対策を義務付け」等がぱちんこへの依存防止対策の課題として掲げられ、先般、出玉規制の強化や管理者の業務への依存防止対策の追加等を内容とする風営適正化法施行規則及び遊技機規則の一部を改正する規則が制定・公布され、来年2月1日に施行されることとなりました。
今回の改正は、ぱちんこへの依存問題に係る実態等を踏まえ、過度な遊技の抑制を図るため、平均的な遊技時間である4時間における出玉率の基準を新設するとともに、従来の規制による出玉率の水準を引き下げ、併せて、いわゆる大当たり時の出玉の上限についても引き下げるものです。また、短時間において、新たに出玉率の下限を追加することにより、出玉の偏りを抑制し、ぱちんこ遊技における出玉の増減の波がより緩やかになるものと考えています。今回の規則改正により、改正規則が施行される来年2月1日以降は改正規則に適合しない遊技機は設置することができなくなります。ただし、改正規則に規定される経過措置により、改正規則の施行後であっても、現行基準による認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機については、当該遊技機の認定又は検定の有効期間が満了するまでは、引き続き、営業所への設置が認められます。規則改正に伴い、都道府県公安委員会に対して、認定申請等が多数寄せられると考えられますが、認定申請等に関する事務処理を滞りなく進めるため、都道府県警察と必要な調整を適切に行っていただくようお願いいたします。
また、現在、業界において、ぱちんこへの依存防止に資する各種取組が進められているところ、今回の改正で営業所の管理者の業務に依存防止対策が追加されることによって、営業所で行われている各種の自主的な取組が管理者の業務として位置付けられることとなります。
営業所の管理者の皆様にあっては、
・ぱちんこへの依存問題の電話相談機関である、リカバリーサポート・ネットワークの営業所内外における周知
・ぱちんこ店の顧客会員システムを活用して、客が1日の遊技の使用上限金額を自ら申告し、設定値に達した場合、翌来店日にぱちんこ店の従業員が当該客に警告する仕組みである、自己申告プログラムの導入
・過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施
・18歳未満の者の営業所立入禁止の徹底
等のぱちんこへの依存防止対策が各営業所において確実に実施されるようお願いします。
先に述べた論点整理では、本改正に関するもの以外にも、
・リカバリーサポート・ネットワークの相談体制の強化及び機能拡充
・18歳未満の者の営業所への立入禁止の徹底
・本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及
・ぱちんこ営業所における更なる依存症対策
等の課題が掲げられており、ぱちんこへの依存防止対策については、これらの課題に係る取組と改正規則とが相まって、総合的に推進されることが重要だと考えています。
論点整理に掲げられた各課題について、既に業界において積極的に取組を進めていただいていると承知しています。
例を挙げれば、「リカバリーサポート・ネットワークの相談体制の強化及び機能拡充」については、今月より相談員等を増員した上で相談時間を延長するほか、ぱちんこへの依存問題を抱えている人は、経済的な問題を抱えていることが多いところ、こうした問題に対応する対面相談会を開始したと聞いています。また、「18歳未満の者の営業所への立入禁止の徹底」については、従来から実施している営業所内の従業員の巡回、監視カメラの設置等の実施に加えて、営業所の賞品提供場所に年齢確認シートを備え、賞品提供時に年齢確認を実施することとし、「ぱちんこ営業所における更なる依存症対策」については、ぱちんこへの依存防止対策の専門員として、営業所に「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」を配置する取組を開始し、既に5千人近くの方が同アドバイザーの講習を受講されたと承知しています。
他方、論点整理に掲げられた課題の中には、現在もその実施に向けて検討が進められているものもあると承知しています。例えば、「本人・家族申告によるアクセス制限の仕組みの拡充・普及」については、自己申告プログラムにおいて、遊技使用上限金額のみとなっている申告対象を遊技時間や遊技回数にも拡大することや、家族からの申告を受け付けること等について検討を進めていただいていると承知しています。こうした検討中の課題についても、できる限り、早期に対策等を実施できるよう業界において必要な検討を適切に実施していただくようお願いいたします。
加えて、論点整理には記載されていませんが、児童の車内放置事案防止対策についても、引き続き取組を進めていただく必要があります。業界では、毎年5月から10月にかけての期間及び年末年始を「子ども事故防止強化期間」として広報啓発を行い、「子どもの車内放置防止対策マニュアル」等に基づいて対策が進められているものと承知しております。
積極的な取組の甲斐もあり、近年は児童の車内放置による死亡事件は認められなかったところでありますが、残念ながら、本年は、5月に山口県、7月に静岡県で、それぞれ乳児と幼児が死亡する誠に痛ましい事件が発生しました。これら事件の発生に加え、例年数十件もの児童の発見事案が続いていることに鑑みれば、児童の車内放置事案防止対策はその徹底した実施が求められていると考えています。
皆様におかれては、今一度、対策が形骸化していないか確認していただき、この対策の趣旨を徹底の上、積極的な防止活動を改めてお願いしたいと思います。また、必要に応じて、新たな対策を検討するなど、今後も更なる実効性のある取組をお願いします。
以上、ぱちんこへの依存問題への対策についてお話ししてきました。ぱちんこへの依存問題は、ぱちんこ遊技の負の側面と言われることもありますが、この負の側面から目を背けることなく、問題解決に積極的に取り組むことが業界の社会的責任であることを強く認識していただき、業界全体で真摯に対応していただきたいと思います。
こうした取組の積み重ねが、ぱちんこへの依存問題の解決に寄与し、国民の理解を得るものとなることを期待しております。
次に、射幸性の抑制に向けた取組についてです。
射幸性の抑制に向けた業界の取組として、製造業者団体が新たな遊技機基準を設け、平成27年6月、全日遊連は、新基準に該当しない遊技機の設置比率に目標値を定め、こうした遊技機の撤去に努めているところであると承知しています。
昨年12月1日を期限に定められていた削減目標値については、営業所全体としては、その目標を達成したとのことですが、営業所別に見た場合、目標を達成できていない営業所が多数あったと聞いています。また、回胴式遊技機については、「メーカー団体が特に高い射幸性を有すると区分した遊技機については、ホールはこれを優先的に撤去する」とした6団体合意のとおりには、必ずしもなっていないという話も聞いており、こうした点について非常に残念に感じていることはこれまでも述べてきました。
本年5月、ぱちんこへの依存防止対策が喫緊の課題となっている現状において、業界が自主的に実施を決めた新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を達成できていない営業所がいまだ存在していること、また、「特に高い射幸性を有すると区分した遊技機」の撤去が進んでいないことは大きな問題であると指摘した上で、6団体において改めてこの課題に対する対応を検討し、その結果を報告するよう要請しました。
現在の目標値設定は、来月1日までとなっていますが、今後は、来月1日以降における、新基準に該当しない遊技機、とりわけ「特に高い射幸性を有すると区分した遊技機」の削減に向けた業界の自主的な取組を早期に決定していただきたいと考えています。
また、こうした経緯も踏まえて、全ての営業所が来月1日の削減目標値を確実に達成していただくようお願いいたします。
ぱちんこへの依存問題等により、ぱちんこ業界に対し、国民から厳しい視線が向けられる中、業界が自主的に実施すると決めたことが実施できないという状況では、ぱちんこが国民の大衆娯楽として受け入れられることは難しいと思います。業界における真摯な取組を期待しています。
次に、「検定機と性能が異なる可能性のある遊技機」の問題についてです。
この問題については、当庁から業界に対し、昨年末を期限に検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の撤去・回収を要請していたところ、業界として、昨年末までの撤去・回収の完遂に向けて努力していただきました。
改めて説明するまでもないことですが、検定制度上、ぱちんこ営業所に設置され営業の用に供される遊技機については、検定機どおりの性能であることが求められており、検定機と性能が異なる遊技機を設置し営業することは制度上許容されていないばかりではなく、極端な場合には風営適正化法が禁止する著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機を設置していることにもなりかねません。
誠に残念なことですが、ぱちんこ営業所において遊技くぎを曲げて検定機と異なる性能を創出する事案は、いまだに継続して発生しております。これまでにも、そのような事案は射幸性の適正管理を侵害する悪質な不正改造事案であると申し上げておりますが、依然、客寄せ等営業者側の都合により入賞口付近のくぎを開け閉めしていた事案が発生しているところであります。
いわゆるIR推進法が国会で審議された際に、ぱちんこ業界に対して大変厳しい意見が述べられたことについては既にお伝えしたとおりですが、このような厳しい現状において、こうした問題が続くようであれば、業界の信用は大きく損なわれ、国民の支持を前提とする大衆娯楽という地位から大きく離れてしまいます。
今回の規則改正では、射幸性の抑制の観点からではありますが、ぱちんこ遊技機にも「設定」の導入が認められたことから、くぎ曲げの抑制にも資するものと考えています。こうした改正を踏まえてもなお行われるくぎ曲げについては、とりわけ厳しく取締り等を行う必要があると考えています。
今後はくぎに関する問題を生じさせないという意識が、遊技機製造業者、ぱちんこ営業者の枠を超えて、業界の方々に広く定着することが必要だと考えております。貴協議会におかれましては、正しい認識を各会員に理解していただくよう周知徹底を図ることはもとより、業界全体をリードして、こうした問題の絶無に向けて積極的に尽力されることを期待いたします。
次に、遊技機の不正改造の絶無についてお話しします。
近年の不正改造の手口は、周辺基板のロムのプログラム改ざん等を偽造ケースや偽造カシメで隠蔽したり、カシメや封印シールを破損することなく、ロムのみを交換する事案が発生しているなど、ますます悪質巧妙化しています。このような厳しい状況の中、貴協議会ではこれまでも精力的に不正改造防止対策に取り組まれ、業界としても不正改造情報の収集や周知徹底、また、これを活かした不正に強い遊技機づくり等の様々な取組が推進されていると承知しておりますが、このような悪質巧妙化している不正事案に対しては、ぱちんこ営業者、遊技機製造業者という垣根を取り払い、事案の情報共有や有効な防止対策を業界全体で模索し、効果的な施策を推進していただきたいと思います。
また、一般社団法人遊技産業健全化推進機構の活動については、業界の健全化に欠かせないものとして、その役割の大きさを皆様も実感しているところではないかと思います。活動開始以来、立入検査店舗数が本年度の上半期までに2万5千店舗を超え、また、検査台数も約18万台を上回り、加えて、立入検査を端緒に検挙に至った事例も多数あるなど、様々な形で成果を挙げています。また、平成27年6月から実施されている遊技機性能調査についても、業界の健全化を進める上で、有意義な取組の一つであると考えています。このような推進機構の活動に対する業界の理解は、徐々に深まってきていると感じておりますが、一方で、いまだに推進機構の活動に対する理解が低い関係者もいると聞いています。
推進機構の活動が効果的に行われるためには、推進機構に対する各店舗ごとの理解が不可欠であり、立入検査を拒否したり、妨害するような行為は、不正改造の根絶を目指す業界全体の取組に逆行する行為であるとの共通認識を更に広め、業界全体で推進機構の活動を支援するなど、不正改造の根絶を目指す気運を高めていただきたいと思います。警察といたしましても、引き続き、推進機構と積極的に連携しつつ、不正改造事犯に対しては、厳正な指導・取締りを推進してまいりたいと考えております。
次に遊技機の流通における業務の健全化についてお話しします。
遊技機の設置や部品交換に伴う手続において、遊技機製造業者が作成する保証書に関し杜撰な取扱いが立て続けに判明したことに加え、不正に改造された遊技機が営業所に設置される事案が発生していたことから、当庁から製造業者団体に対し、遊技機が各営業所に流通する過程においても型式の同一性が担保される制度の構築と、その運用に関するルールの明文化を要請したところ、製造業者団体において、「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」が制定され、昨年4月より運用が開始されました。また、この要綱等の施行後、製造業者団体が、ぱちんこ営業者向けに「遊技機流通健全化マニュアル」を策定し、各種研修等も行われているものと承知しています。運用開始当初は不慣れな対応によるミス等が生じたと聞いていましたが、現在は制度の理解も進み、不備も減少していると聞いています。遊技機の流通に携わる関係者が正しく制度を理解するよう、繰り返しの研修の機会を設けるなどの取組を継続していただくとともに、今後も個々の運用を通じて制度の不備等が考えられる場合には、必要に応じて制度の更新も視野に入れるなど、遊技機の流通における健全化を一層図っていただきたいと思います。
昨年4月以降に販売された型式の遊技機については、部品交換の際、変更承認申請に係る保証書の担保として、遊技機の状態が検定機と同一かどうかの点検確認を遊技機製造業者等が一台一台実施することとなりました。また、遊技機の営業所への設置時や部品交換時に行う遊技くぎの点検確認は、これまで目視で行われていたところ、今年4月以降に新台として設置されるぱちんこ遊技機から、目視による確認の補助として「くぎ確認シート」等の器具が使用されていると承知しています。こうした取組により確認の精度も向上し、遊技機流通の健全化も進むものと考えています。くぎ確認シートの中には、全ての遊技くぎを対象としていないものがあるなど、各製造業者で区々であるとも聞いておりましたが、現在、改善に向けた検討を進めていただいていると承知しています。今後、運用を通じて更に改善を進めていただくようお願いいたします。
新たな流通制度を厳格に運用することは、射幸性の適正管理につながるものであり、ぱちんこへの依存問題対策においても大きな意味を持つものであります。保証書の厳格な取扱いが遊技機の射幸性の適正管理に必要不可欠であり、検定機として遊技機を営業所に設置し、都道府県公安委員会の承認を得ている以上、検定機と同一の構造・性能の遊技機を置かなければならないことを改めて認識していただきたいと思います。
今後も、新たな流通制度が現場にしっかりと根付き、業界の更なる健全化が進展することを期待しております。
ここまで縷々述べてまいりましたが、ぱちんこ産業は、遊技人口が減少傾向にあるとはいえ、なお、非常に多くの方々が参加している娯楽産業であります。課題は山積しておりますが、ぱちんこへの依存防止対策を最優先課題として位置付けるとともに、その他の課題についても、一つ一つ迅速かつ真摯に対応していただきたいと思います。その実現なくして、ぱちんこは健全な遊技たり得ないと考えます。
いまだにこれらの取組に消極的な関係者が一部にいることについては、極めて残念なことと言わざるを得ません。今一度、ぱちんこ業界が置かれている状況について思いを至らせ、お一人お一人が能動的にこうした問題に前向きに取り組むことが、ぱちんこ業界のためになることを認識していただきたいと思います。今後のぱちんこ業界の皆様の御努力に期待いたします。
結びに、貴協議会のますますの御発展と皆様方の御健勝、御多幸を祈念いたしまして、私の話を終わります。御静聴ありがとうございました。
==========
 LINE
LINE