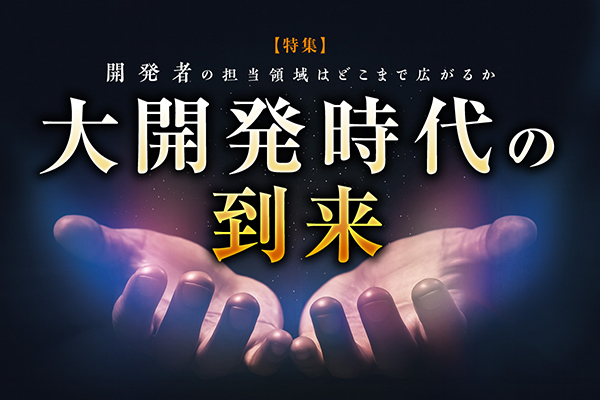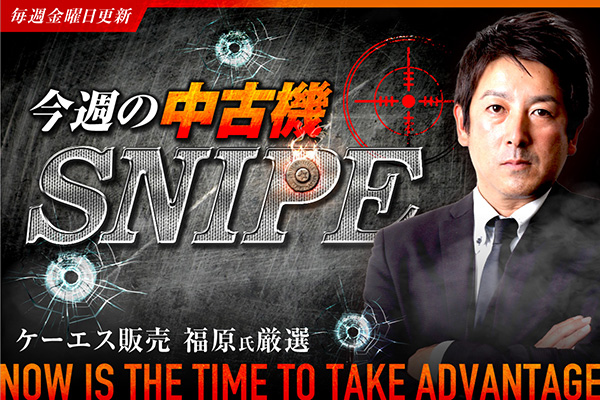大開発時代の到来 開発者の担当領域はどこまで広がるか【後編】
2025.08.20 / メーカーCASE3:株式会社コナミアミューズメント
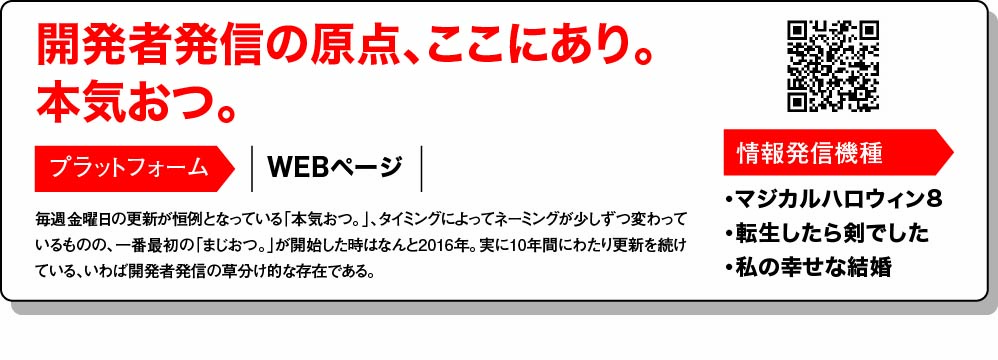
続いて編集部は、株式会社コナミアミューズメントの開発チームの皆さんへ突撃取材を行なった。
「本気おつ。」の運用は完全に開発チームで完結!
編 現在運営している「本気おつ。」は、どのような体制で運⽤が⾏われていますでしょうか。
KONAMI開発チーム(以下、K) 「本気おつ。」の運営については、「マジハロ」シリーズの制作チームが文章作成および構成を行い、制作部にて内容のチェックを行ったのちにHPチームにてWebページの作成および公開を行っております。広報チームは外部メディアに対しての業務が主なので切り分けています。
編 現在「本気おつ。」の運⽤を⾏なっている狙い、⽬的はなんでしょうか。また⼀番初めに「まじおつ。」の運⽤を開始した時の狙いや⽬的はなんでしょうか。
K コナミの商品をユーザーがより楽しく遊んでいただけるよう、情報を発信していくためです。
遊技機の情報は外部メディアから得られるものが多いかと思いますが、その中でも遊んでいて分からないこと(公開されていないこと)もたくさんあると思います。そういった遊技の中での分からないことを解消して、全力で商品を楽しんでもらうのが狙い、そして我々の願いです。
遊技機メーカーはホールに機器販売するという面でBtoBビジネスであり、「本気おつ。」(2016年スタート時は「まじおつ。」)を始めた2016年の段階では業界的にエンドユーザーであるプレイヤーとの関わりはあまりありませんでした。ユーザーが情報を得られるのは雑誌をはじめとするメディアのみで、情報は一方通行で限定的なものしか得ることができない状況だったと記憶しています。
自分もパチスロを打っていて知りたいことが出てきたりするのですが、雑誌やWebを調べても出てこないものがほとんどで、これを聞ける場所も存在せず、分からないものはしょうがないとモヤモヤは残したまま諦めていた状況でした。そんな経験から、ユーザーからの質問をメーカーが直接回答してくれて知りたいことが聞ける場所は需要があると考え「まじおつ。」のQ&Aを始めました。知りたい情報を得たらまた打ちたくなる可能性もありますし。
あと、こういう取り組みをしているメーカーは当時まだ無く、これをやることによってメーカーとユーザーの新しい関係性が生まれそうで面白そうと思ったというのもありました。
各施策の決定権は商品プロデューサーにあり!
編 開発チームは遊技機の販売において、広報的・営業戦略的な施策⾯にどのように関わっていますか。
K 商品プロデューサー(機種開発チームのトップ)が中心となって販売プロモーションを策定します。プロモーションプランの案は、開発チームや販売・広報チームと一緒にアイデア出しながら検討し、決定していきます。最終的なプランの採択は商品プロデューサーが行います。
営業戦略に関しても、戦略の策定こそ販売部が行うものの、こちらも商品の最終責任者は商品プロデューサーになっているので商品プロデューサーの合意の元に決定いたします。
まとめ
「本気おつ。」に関してはなんと内容のチェック含めて開発チーム内で完結という運用であった。ある種独立した発信媒体を開発チーム内で持っていると言っても過言ではない。
そのような体制を敷けるのは、もちろん開発チームの影響力の大きさの面もあるだろうが、開発チームと広報チーム含め他の部署との信頼関係があるからこそ成り立つ仕組みであるとも言えるだろう。
他社と比較すると、開発チームの商品プロデューサーを中心に意思決定を進めているため、より開発チームの影響力が大きい印象だ。

CASE4:ニューギングループ開発部
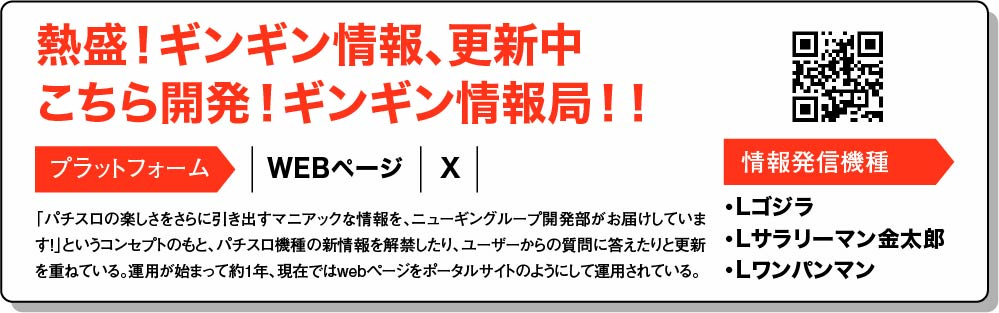
続いて編集部は、ニューギングループの開発チームの皆さんへ突撃取材を行なった。
遊技するユーザーとの信頼関係が最優先!
編 「ギンギン情報局」はどのような体制で運⽤が⾏われていますでしょうか。
ニューギン開発チーム(以下、N) 開発チームの担当者が記事を作成した後に、チェック担当者が記事の内容を確認しています。開発チーム責任者・広報チーム・渉外チームがそれぞれ確認していますね。
編 「ギンギン情報局」の運⽤を開始した⽬的は何でしょうか。
N 大きく分けて2つありまして、1つはユーザーに対して、メーカーならではの情報を直接発信する場を作ることです。従来の情報伝達手段では届きにくかった有益な情報を、タイムリーかつ正確にユーザーへ届けることを目的としています。
もう1つはユーザーが抱える疑問や不安に対して、メーカーが直接回答できる仕組みを構築することです。双方向コミュニケーションを実現することで、信頼性の向上と業界全体の透明性の確保を目指しております。
編 運用にあたって気をつけていることはありますか。
N こちらも2つありまして、1つは新台の市場導入日の前後において、ユーザーがより楽しめるような多様な情報を高頻度で発信することです。新機種に関する情報をタイムリーに提供することで、ユーザーの期待感を高め、より充実した遊技体験に繋げることを目指しています。
もう1つは、寄せられたご質問には、可能な限り迅速に回答することです。ユーザーとのコミュニケーションを円滑に行うことで、信頼関係の構築と満足度の向上を図っております。
編 「ギンギン情報局」では、開発チームが本来⾔いたいことの何割程度の情報出しが実現していますでしょうか。
N 現時点において、開発チームとしては「ギンギン情報局」を通じて、公開可能な情報はほぼ全て発信できていると認識しております。
情報の精査にあたっては、ユーザーの理解促進と興味喚起を重視しつつ、製品の魅力を最大限に伝えることを目的としております。今後も、より分かりやすく、かつタイムリーな情報提供を目指して運用を継続してまいります。
他社より控えめ?
技術がものを言う範囲で協力!
編 開発チームは、「ギンギン情報局」以外の⾯では、広報的な施策にどのように関わっていますか。
N 施策については、広報チームが主体となって立案しています。機械に関わる内容などについては、開発とも共有しており連携して進めるケースもあります。
編 では開発チームは、営業戦略的な側⾯では、どのように関わっていますか。
N 販売前の試打であったり、デモ機制作であったりなど、開発として販売に関わる部分で連携しています。直接的に販売計画に関わってはおりませんが、営業の皆さん、たくさん売ってきて!って思いながら応援しています(笑)
まとめ
全体を通して、実際に台を遊技するユーザーとの信頼関係を構築することが優先との回答だ。ユーザーとのタッチポイントが限られているだけに、双方向のコミュニケーションはやはり重要なものとして開発チームも認識している。
また、同社では台に関して「稼働貢献する機械を市場に提供すること」を最も重要な使命として掲げているという。そのためには初期稼働の獲得・継続稼働の維持の2点を重要視しているとの話だが、「ギンギン情報局」の運営はこの2点を底上げするという役割も当然あるのだろう。
運用が始まって1年ほどだが、「ギンギン情報局」を開設した際の目的は今の所順調に果たされているように見える。

匿名だからこそ話せるネタ!?
謎の開発者X氏と本音居酒屋トーク
メーカー開発インタビューの最後は、所属メーカーを含め完全に情報出しNGの匿名開発者の方(以下、X氏)だ。近年はYouTubeでの顔出し解禁などメーカーによっては風向きが変わってきているところもあるが、元来遊技機は機密情報の塊であり、その開発に携わる技術者は身元を含め秘匿される傾向があるのは変わらない。一方で、X氏のように完全に身元を隠した状態だからこそ回答できる質問もあるはず。ここでは「スマスロの開発」および「開発者として重要なマインドとは何か」について聞いてみた。あくまでX氏の個人的な見解だという点にご留意いただきたい。

パチスロ開発の難しさは一点を狙う精密さにあり
そもそも、パチスロ開発は難しいことなのだろうか。案外ノウハウさえ参考にすれば誰でもできることなのでは。そんな疑問について、X氏は「素人には無理」である旨の回答をしてくれた。
台を作るのは年々難しくなっており、対応できる開発者の希少価値は存外高いという。特に現在のスマスロ時代においては、狙ったスペックをピンポイントで開発する必要があるようだ。少し前の規制下では、開発途中で少しだけ数値を変えて調整するということができたが、今の時代の開発はその少しの調整すら許されない環境である様子。
良い開発者とはなにか 初めから持つべきもの
X氏が思う「良い開発者」とはどんな人間だろうか。訊ねてみると「開発中に『できた』と言わない人」だという。
真の技術者とは納期前に完成するのを良しとせず、限られた制限時間内に最大限面白くなるような創意工夫をギリギリまで続ける人を指す。したがって途中で「できた」と考えるのは遊技機開発者としてタブーなのだそうだ。
また、マインドの部分で言うならば「熱意を持つこと」が開発者として重要なのだとX氏は述べる。熱意であれば、多くの開発者が持っているのではないか、一瞬安易にそう考えたが、ここでいう「熱意」とは、ただちょっと「好きだ」程度の生半可なものではない。パチスロの開発が人生の一部だと考えるほどの熱意だ。実際に開発の現場では、趣味の一環として開発を行っている人も多い印象だと言う。
さらに言えば、開発の技術的な部分は経験を重ねる中で後からでもいくらでも身につくものだと言う。しかしこと熱意に関して言えば後から勝手に身につくものではない。そういった意味でも熱意という要素は非常に重要であるとX氏は述べる。
他部署と開発の食い違い
そのような「職人肌」の開発の場合、往々にして営業担当とは衝突するらしい。なんせ営業担当はその職責上の特質から「今」の市場と現場を見ているが、開発は販売後の稼働、つまり今より先の「未来」を見据えて開発に取り組む必要があるからだ。
この衝突は、ある意味では開発が営業の領域に片足を踏み入れているとも言え、単に「機械を作るだけの人」というイメージとは遠いだろう。場合によってはデータを集めて営業担当の意見に対して論理立てて真っ向から反論することもあるようだ。
一方で、X氏は所属している企業に対して感謝をしているともいう。やはり企業には機械の開発の地盤があり、販売できる販路があり、ユーザーに対する訴求力もある。当然自分一人では開発なんて進まないし、市場に流通させるにまで至らない。成果を出す土壌も、成果を見せる土壌も整っているとX氏は述べる。
”異端児”の味方でありたい
開発者としての考え方で、全体のバランスをとるよりも、何かひとつの強みや個性を伸ばしていく人の方が、後々ヒットメーカーとして活躍しているとX氏は分析する。しかしそのような人材は貴重である反面、周囲との考え方の違いから少数派の立場をとることも多いという。
データをもとに周囲の多数派を巻き込みながら自分の考えを通せれば良いのだが、やはり多数派を相手にする分乗り越えねばならない壁が高いのもまた事実だ。
そんな時にその人材に寄り添って、力になってあげる。自分が認める立場になって将来のヒットメーカーの個性を伸ばす。そんな存在でありたいとX氏は述べる。開発において少数派の意見を抑えることは簡単だが、将来の開発の至宝を失うのも非常に惜しい。X氏は目の前のプロジェクトだけでなく、会社およびパチスロ業界の将来をも見据えていた。
開発チームの担当領域は、もはや遊技機の開発のみに収まらない。
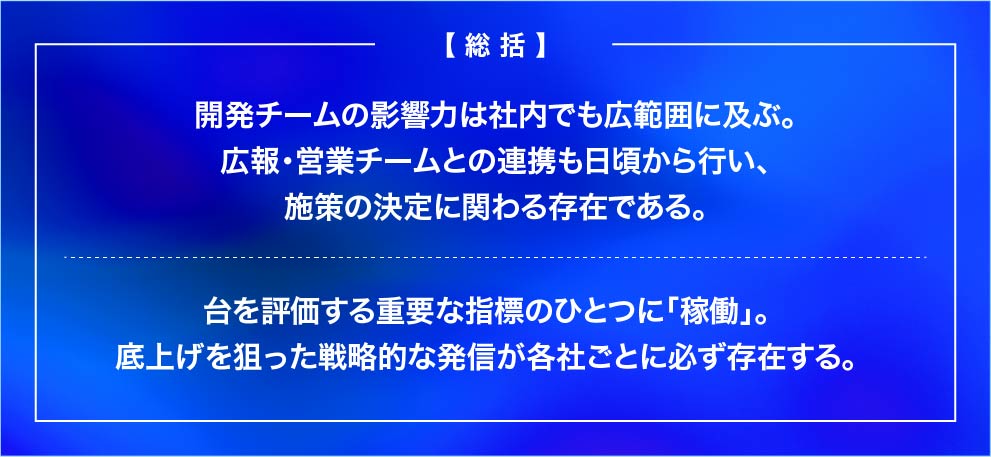
大開発時代の到来 その時ホールにできること
開発チームの力は広報や営業にまで影響力を持ち、企画やプロモーションを含めて、まさに台のゆりかごから墓場までを設計する開発者の思想や好みは、そのメーカーの特色にダイレクトに反映される。さらに細分化するとメーカーの開発プロジェクトはチームごとに複数動くのが常であり、同じメーカーの台でも機種によって異なる色を見せている。
もし仮に開発者が表に出る機会が増えるのであれば、「あの人(あのチーム)が作った機械だから買おう」といった、同じメーカーでもより細かな「指名買い」のような買い方が増えるかもしれない。購入機械の選定はいつの時代も店長の頭を悩ませる業務だが、台数を決める材料がひとつ増えるとなると、これは無視できない話だ。
実際、近年は過去ヒットした機械のリバイバルが増加していることもあり、「初代のチームが集結」のようなあおり込みで営業が行われることも増えてきた。これが進めばリバイバル機ではなくとも直近のヒット作を例に「◯◯を作った◯◯氏が制作総指揮!」のような扱いを受ける、さながら「スター開発者」の登場もあるかもしれない。同様に、ユーザー間でも個々の認知度が高まってくれば「指名打ち」のような現象が発生する可能性も十分考えられるだろう。なんせここまで開発者の力が増し、どんどん表に出るような時代は長い業界の歴史の中でも初のことなのである。
常識がどう変化するかは、誰にも予測ができない。前述のような「スター開発者」が実名で出るようになる可能性は決して低くなく、それが広報・営業に利用されるようになるのも、いかにもあり得る未来である。実際に同じエンタメ業界のゲーム制作においては、神格化されたプロデューサーまで存在している。そうなった時に「知りませんでした」は通じない。台の生産数は有限なのだ。機会損失を避けるためにも、購入機械の選定に関わる店長は、今のうちから開発者の声に耳を澄まし、彼らがユーザーとどう関わり、どのような台をどのように作っているかを把握しておくべきだろう。開発者こそがすべてを支配する「大開発時代」の到来は、もしかしたら目と鼻の先にまで迫っているかもしれないのだ。
開発者インタビューは継続して実施予定!
今回、取材のタイミングが合わずにお話を伺えなかったメーカー様も多数存在しています。今後はお話を伺うことができましたらwebやXでの掲載を想定して、引き続き開発インタビューを実施していこうと思います。
 LINE
LINE