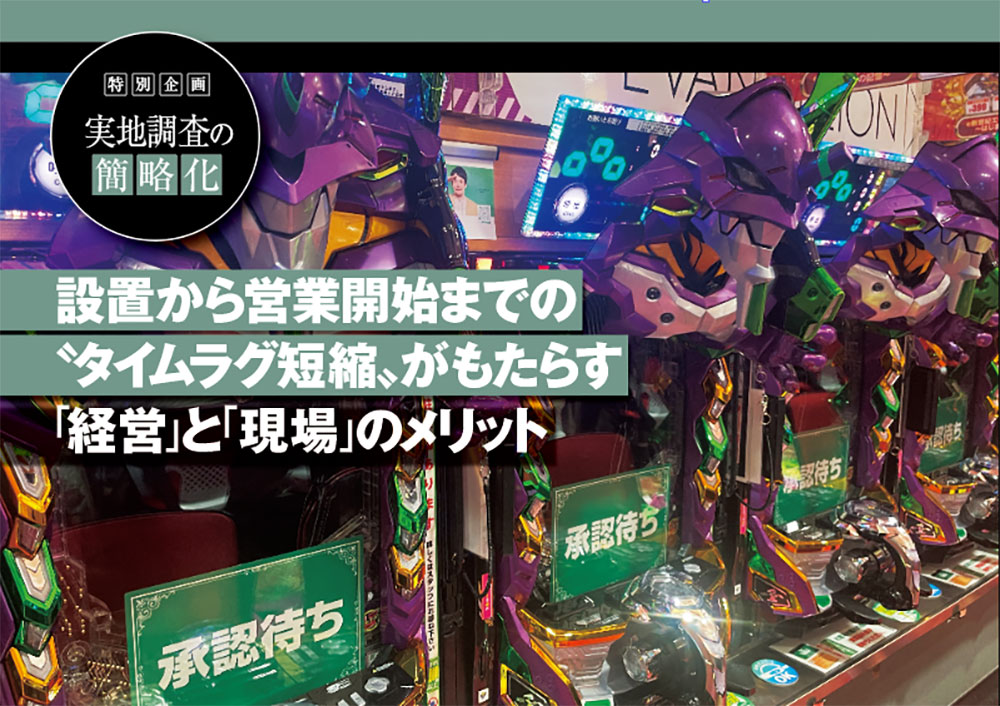宮城県屈指の強豪企業、カツヨシ商事の戦略と思想とメルヘンワールドの双璧
2025.09.19 / ホール東北地方を中心に13店舗を展開するホール法人、カツヨシ商事の旗艦店「スーパーメルヘンワールド幸町店」は、周年日の4月27日に、オープン2時間前に2000人を超えるユーザーを集め、今では宮城県屈指のホールとの呼び声も高くなっている。この輝かしい実績の裏には、SNSを中心に顧客と密接なコミュニケーションを取り、方針を決定していく営業本部執行役員統括長がいる。アカウント名は「ハンレツのぬさん」。そして、ぬさんの方針を支持しつつ、琴亮吉(クン・リャンギル)社長とのコミュニケーションを円滑に行い、非常に重要な社内の調整役を務める大山早人氏(営業本部管理長)。今回は会社を支える2つの頭脳を取材しメルヘンの強さに迫る。

社長決裁のない経営!?
社長の「任せ力」が生んだ奇跡の法人
カツヨシ商事が変わったのは2015年のこと。会社の閉塞的な雰囲気をなんとか変えようと、当時一般社員だったぬ!氏が決意のメールを全店送信した。琴亮吉社長はその直訴に真摯に向かい合い、ここからカツヨシ商事の空気がガラリと変わった。ここが分岐点だった。そのストーリーを追っていく。
パチンコ業界では「家業」として遊技場を運営する会社は依然として多く、このパターンではともするとワンマン経営となりがちだ。これに対して実質的な経営の舵取りを現場側に委ねて、成功している事例はあまり多くないかもしれない。
8P(本誌)の紙幅を割いてお送りする本企画の結論である「なぜカツヨシ商事は強くなったのか」を最初に述べるならば、この営業の指揮権を現場責任者に委ねたという一言に尽きる。それでは振り返っていこう。
かつて、カツヨシ商事の代表取締役社長琴亮吉氏の父は、一代にしてカツヨシ商事の礎を作り上げた。人格者ではあったが、そのたゆまぬ努力はいつしか経営に大いなる厳しさをもたらしていた。というのも、あらゆることを社長が決定するという風潮だったのだ。「今日はあの台で頑張るんや!」と、毎朝社長から各店舗にホットラインが飛ぶと現場を任された店長は逆らうことはできない。この他にも、頻繁な電話やメールでの途中報告を求めたり、緊急会議を開催するなど過干渉な状態に陥っていた。
こうなると、会社内には顔色うかがいの風土が色濃くなり、社員は自ら考えることを諦めてしまう。そんな空気感が全方位を包んでいた。父の経営を目の当たりにした琴亮吉氏にも、父から厳しく指示が飛んできていたが、自らが経営者になったばかりの頃は、社員に対し厳しく接していた。当然、部下は次々とドロップアウトしていく。原因は明白だった。

ところが、2015年にある事件が起こる。ことを起こしたのは、現在カツヨシ商事の営業権のほぼ全権を握る執行役員営業統括長のぬ!氏だ。ぬ!氏は業界歴30年、カツヨシ商事でのキャリアは17年目という功労者で、アルバイト時代から別法人の店長を見ながら「俺だったらこうするのに」と自身のアイデアを磨きながら働き、ホール運営の勉強を続けていた。ある程度キャリアも長くなり、初めて店長就任の話を持ちかけられた際、ぬ!氏はこの話を断ったという。
「当時のカツヨシ商事は、旧態依然とした年功序列の制度でした。店長就任の打診を断った理由は会社の人の扱いや評価制度に不満があったからです。当時、カツヨシ商事は店舗拡大路線を推し進めていた時期で、埼玉県にも勢力を伸ばそうとしていました。社内で埼玉で勤務してくれる人材を募ったのですが、蓋を開けてみれば誰も手を挙げません。会社を愛し、会社に尽くそうという従業員がほとんどいなかったんです。もちろん(先代の)社長は一代で築き上げた商才があり、人情味があって、厳しくも熱い方でした。それゆえ、下の声が届かない社内風潮にもなっていたんです。周りも意見できなくなってしまっていたので、これは誰かが言わないとダメだと思い、自分が言うことを決意したんです」(ぬ!氏)

一念発起したぬ!氏は自身の進退をかけて、社員を代表して「このまま全国展開を考えるのであれば、いまの会社の仕組みは変えないといけない」と全社にメールを一斉送信した。ぬ!氏は会社のことは好きだったし、周りで働くスタッフとの仲も良かった。可能であればこの先もずっと働きたいが、何も言わなければ不満を抱えたまま働き続けることになる。このメールで経営陣の逆鱗に触れてクビになるならそれでもいい。しかし、それで会社が変わるのならと願った。ほとんどギャンブルだった。
メールを送った翌日、当時常務だった琴亮吉氏に呼び出された。即刻クビになるかと思ったが、意外にもそうはならず、訴えを聞き入れてくれたのである。この時の心情を、琴社長はこう振り返る。
「彼は多少生意気な部分がありますが、それは会社を想ってのことだというのはすぐに分かったので、こちらも真剣に話を聞くことにしたんです」
ぬ!氏は社長に対して、真っ向から意見を述べることができる異端な存在だった。「それは違うと思います」「なぜ分かってくれないんですか」。時に感情的になることもあった。言葉を受け取る側次第では、激昂されたとしても仕方のないレベルのコミュニケーションだ。
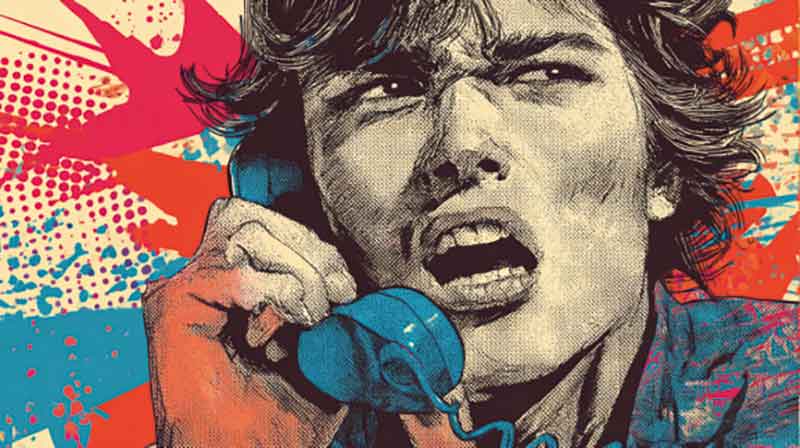
「でも、その言葉は他の社員の気持ちの代弁であり、現場で結果を出せるという自信があることも感じられました。だから『まずは落ち着きなさい』と冷静になだめて、ちゃんと話を聞こうと思いました。そうしたら彼も『感情的になってすみません』と冷静に話を始め、訴えの内容も理解できたので、『じゃあその方法で一度やってみようか』と、任せることを決断しました。もちろん、その代わり結果が出なかったらこうだよという責任も含めてですね」(琴社長)
そこからは少しずつ会社が変わっていった。以前は毎朝直接社長が店舗に電話し「今日はこうしろああしろ」と細かく指示出しがあったが、まずはこれを廃止。月次の結果と主要数値の変動のみを見ることにした。各種目標数値については月次報告はあるが、それ以外については年単位で個々の店舗・社員の考えに任せるという、個人個店の考えや思考に期待と責任を与える方針ではあるが、ある意味では放任主義にも見える独特な経営だ。
結果主義への路線変更の影響は給与体系にも及んだ。年間予算の達成率と報酬を連動させ、ボーナスなどの査定も分かりやすく整理。もちろん高い報酬だけでなく社内では相応の模範的な姿勢も求められるし、会社への貢献が低いと判断されれば降格や配置転換も辞さないという「責任」も明文化された。年功序列の空気を刷新するべく、「率直な進言を歓迎する」というポリシーまでをも掲げ、会社は大きく変わった。
とはいえ、いくら経営陣に理想を説いたとて、自分が理想通りの店作りや業績を達成できないならばそれは絵に描いた餅にすぎない。ぬ!氏の奮闘はここからが正念場だった。件の決意のメールの直後、200台程度の小さな店を任された。打ってもなかなか響かない、難易度の高い店舗だった。
ぬ!氏の営業力の源は、顧客とのコミュニケーションの巧みさにある。かつて駆使していたのはブログだったが、現在ではプラットフォームをSNSに変え、常に話題性のある店舗を実現する。

任された店舗については、まずは、「昭和のパチンコホール」というイメージから変え、店内の動線を整理し、ブログやメールを活用して常連客と心を通わせ、それに合わせたイベントを企画した。文字に起こすと極めてシンプルな戦略ではあるが、2カ月で売上は倍になった。
小規模店での勤務は半年ほどだったが、この間業績はずっと右肩上がりであり、ぬ!氏の大車輪に、会社の士気も高まっていった。本格的に「任せる」「評価する」という方針が固まっていったのはこの頃だった。ぬ!氏自身も、その営業力を買われすぐに旗艦店へ異動となった。
この変化で大きくメルヘンワールドの営業を変えたのが、意思決定から実行までのスピード感だ。社長とぬ!氏、そして後述する営業管理長である大山氏の間でまずは数字の目標を先に決める。その実現に向けての細かい話は現場側で詰めていく。このプロセスの中で、「社長決裁」を排除しているのが特にカツヨシ商事の経営の面白いところだ。社長は枠組みを作り、最終的な判断のみを行うが途中で口は出さない。すべては結果を見て判断する。このシンプルさは見習いたい会社も多いことだろう。
こうして、メルヘンワールドという組織体の頭脳が再び動き始めたのである。営業で成功を収めたぬ!氏は、この後もことあるごとに社員から担ぎ上げられ、社長に意見をするフィルター役として活躍している。店長1人の意見としては声が届きにくくても、ぬ!氏を筆頭に現場サイドで意見をまとめて代表して具申する。
現在、チェーン全店の営業方針の決定や企画立案、現場裁量の承認から最終決裁までを一手に引き受けているほか、ご存知のようにSNSなどによる顧客コミュニケーションの方針策定も行っている。まさに店舗営業に関することについてはほぼすべての実権を握っている。
ぬ!氏が自由に動けるのはこの人がいるから。
耳慣れない「管理長」というポジションの役割とは
琴社長は、ぬ!氏に全権を委ねつつも、「営業管理長」という独自のポジションを用意した。任されたのは若い時分からぬ!氏の直属の部下となることも多かった大山氏。本人すら管理長というポジションに対して、「最初は何をする役割なのかがよく分からなかった」と答えるが、実は会社にとってなくてはならない調整弁なのである。
社長とぬ!氏の話を聞いて、カツヨシ商事においてぬ!氏は強い発信力と行動力で直接社長へモノを申しながら率先して売上を作っていく役割だということが分かった。現場の発言力が強く社長の決裁が不要な組織というのは意思決定が早く問題が起きた時のフォローも迅速だ。売上や顧客満足につながる施策の立案と実行もテンポよく行えるので、ある意味では理想の風土だとも言えるが、一方で間違った方向に進んだ時やバランス感覚を失った時に俯瞰して問題を解決するブレーキ機構が不在という危うさも秘めている。
そこでカツヨシ商事では、ぬ!氏とは違った形でもう一つ会社の舵取りを行う頭脳が用意された。それが琴社長が「守備力の大山」と表現した管理長・大山氏だ。
管理長という、パチンコ業界では耳慣れない役職は2023年に新しく作られたポスト。文字通り直接的な利益面のコントロールを行うことを目的としている。攻めの姿勢で売上を伸ばす役割のぬ!氏に対し、経費の面からときにブレーキ役になる役割だと言えば分かりやすいかもしれない。

そんな管理長に抜擢された大山氏はぬ!氏とは直接の後輩・先輩の関係だった。大山氏が入社した時、すでにそこにはぬ!氏がいた。ここ10年ほどはぬ!氏とは違う管理部門に所属していたが、2年半ほど前に突如社長に呼ばれ「こんなポストを用意したから」と突如告げられたのが件の「管理長」だった。
「管理長ってなんだろうと思いました(笑)。何をするのか最初はよく分からず困惑しましたが、要は利益面のコントロールです。ぬ!が決めた営業方針に対して『ちょっとそれ利益が足りないんじゃないですか?』みたいな感じでバランサーになる役割なのですが、それも社長とぬ!の方で話した結果、そういうポストが必要だろうということで作られたようです。いわば経営と現場の中間役。社長からは『とりあえずうまくやってくれ』と言われました(笑)」
大山氏はアルバイトから入社して店長も経験し、そこから本社に行き経理を中心にキャリアを積んできた。とはいえオープン前の大型店舗の店長をぬ!氏から話を受けて突如やることになるなど、要所要所で重要なポジションで指名を受け、それらをすべてこなしてきた。その結果、「いつのまにか会社から信用される存在になっていたかもしれない」と自らの立ち位置を分析した。
環境の変化がやや苦手な大山氏はこの指名に戸惑いもあったそうだが、自分が選ばれたのには何かしらの理由があるのだろう思い、数日かけて「とりあえずやってみるしかない」と強引に飲み込んで腹落ちさせた。このある意味で懐が深く、器の大きい性格が、アクティブなぬ!氏の手綱を握るのには適していた。
ちなみに大山氏についてぬ!氏はインタビュー中、「お金の管理をしている管理長がとても優秀なので自分が好きに動くことができる」という旨のことを繰り返し述べていた。まさに二人三脚。頼れるバディである。
一方でカツヨシ商事という会社にとってのぬ!氏の存在について、大山氏はこう表現していた。
「社長にメールで気持ちを直接伝えたという話からも分かるのですが、社長としても自分に直接モノをいう社員がいなかったので、逆にぬ!を信頼するキッカケになったのは間違いないと思います。そのぬ!と上手くコミュニケーションが取れる自分がこのようなポストにつけてるというのは、理解できます。ぬ!はカツヨシ商事にとって絶対に必要な存在です。ぬ!のお客さま、会社、社員に対する考えが浸透し、ぬ!のような社員を教育をしていくことが、今後会社がもっと成長していくためには重要な課題かなと思います」

現在、カツヨシ商事はトップの社長の真下にぬ!氏、そしてその横に大山氏というイメージで動いている。各店舗はぬ!氏の直轄にあり、大山氏は本社でそれらを監査するという形だ。そしてもう一点、ぬ!氏が暴走せず実力を発揮できるよう、適切にコントロールし、ときにはブレーキをかけるのもまた、「守備力の大山」氏の大切な役割なのである。またその他、大山氏は現在、機械代や設備投資の管理、店ごとの利益配分や月次調整、そして短期的な資金繰りの最適化などを一手に担っており、バックグラウンド業務の最終責任者となっている。
会社を変えた、経営者の心意気1つ。
琴亮吉社長の苦悩と任せる主義
ここまでは会社が変わったという「結果」を追ってまとめてきたが、今も続くこのストーリーを形作ったのが琴亮吉社長である。経営するパチンコホールは全部で13店舗。現場を「任せる」決断は並大抵のものではなかっただろう。社長が見せた胆力の裏で考えていたことを語ってもらった。
自分も一社員として現場を任されていた頃、父である先代の社長からは厳しく業績を求められた。そんなにすぐに売上が上がる世の中はないとも分かっていた。ある意味で不条理とも言える経験してきていたはずなのに、自分が経営サイドに回ると父と同じようになっていた。これはおかしいということでまず冷静になれて会社を変えることを決断した。
その後必要になったのは、我慢する力だった。ぬ!氏は会議の場でも熱くなりやすい。

「意見が割れた時に、私に向かって大きな声を出して、机をバーンとやったり、失礼ですよね(笑)。でも、彼の感情を汲んでその心に入っていくと、『俺も親父にやったよな』とフラッシュバックするんです(笑)。で、どっちが正しいかと言うと現場が正しい。自信があるから社長にも強気に出れる。感情的になって涙を流して訴えてきたこともある。本当に社員やお客さまのことを考えて提案や意見を述べてくれているんだなと」(琴社長)
ただ、大きな権限を与えるからには、相応の責任を求めることは必須だった。会社はあくまで組織だ。プロ野球で例えるならば、年俸5億の選手が打率2割前半でベンチで偉そうにしていて、方や若手が3割打ってるのに遠慮するみたいな風潮になってはいけない。琴社長はグッと手綱を締めた。
「社長の仕事ってそこですからね。人をどう起用するか。店長がいつも数字を見て考えてくれているわけだから、それを信頼できないんだったら一軍に入れちゃダメですよね」(琴社長)
営業を現場に任せたり琴社長の経営には柔軟性がある。2015年に先代の社長が亡くなり、会社を引き継ぐことになった時に、会社を大きく変えた。パチンコバブル期に店長になった人たちや、先代との付き合いだけで大した提案もなかった士業の人たちを切った。
「士業の先生方も何人もいたんですよ。あまり会社にとって利がなかったので、自分が社長になったことをきっかけに取引をやめたいという話をしたら、去り際に『その年でそういうことやるとバチあたるから』と暴言を言われたこともありました。でも、『今までありがとうございました』と頭を下げ続けて退席していただきました」(琴社長)
このエピソードからも分かるように、琴社長は変化に対して柔軟であり、その変化に耐え忍ぶ胆力がある。良い意味で社員を泳がし、実力を発揮してもらう。SNSの運用なども最初は、「これはツイートして大丈夫なの?」と感じたこともあったが、口出しするのはやめた。報告なしに、現場が自分の考えで物品を買ったりしたこともあった。
「もうね、見てしまったらたまらなくなりますから、見ないようにしています(笑)。現場は店のために、会社のために発信をしているから信じるしかない。経営してる社長さんたちは自分の思いもある。パチンコ業に対する思いもある。人は人。自分は自分。私は口出しをせずに耐えた方がいいと思います」(琴社長)

ぬ!氏が送った一通のメールから始まったカツヨシ商事の改革。独自の経営を実現させた琴社長、ぬ!氏、大山氏。現在の好調は、この3名の絶妙なバランスで成り立っている。
 LINE
LINE